令和7年秋季特別展
繕いの茶道具
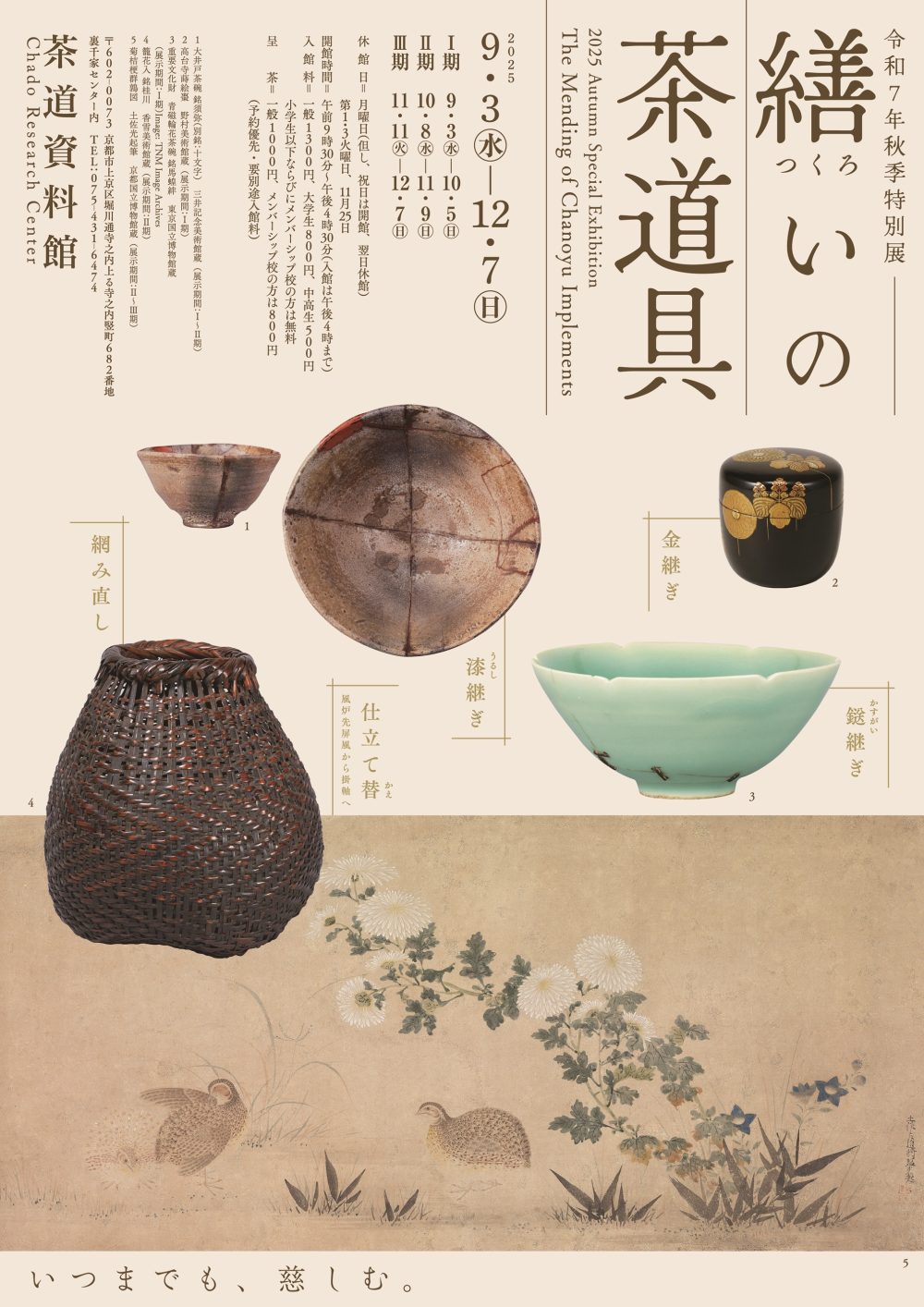
ダウンロード
長い年月のなかで、多くの人の手を経て守り受け継がれてきた茶道具は、幾度となく破損の危機に晒されてきました。戦乱や災害、経年変化などにより本来の姿形を変えた後も、丹念に繕われることで新たな魅力を放つようになります。また、繕いを意匠として取り入れた茶道具も誕生しました。それらからは、所有者の道具への愛着や好みを窺い知ることができます。 本展では、金継ぎ・鎹継ぎ・呼継ぎ・編み直しなど、さまざまな技法で繕われた茶道具を紹介し、今日の姿に至るまでの歴史とその魅力に迫ります。茶道具のあり様に寄り添い続ける茶人の思いや、繕いの痕をもいつくしむ美意識を見つめ直す機会となれば幸いです。
会期 | 令和7年 9月3日(水)~12月7日(日) Ⅰ期:9月3日(水)~10月5日(日) Ⅱ期:10月8日(水)~11月9日(日) Ⅲ期:11月11日(火)~12月7日(日) |
開館時間 | 午前 9 時 30 分~午後 4 時 30 分(入館は午後 4 時まで) |
休館日 | 月曜日(但し、祝日は開館、翌日休館) 第1・3火曜日、11月25日 |
入館料 | 一般1,300 円、大学生 800 円、中高生 500 円 小学生以下ならびにメンバーシップ校の方は無料 |
呈茶 | 一般1,000円(要別途入館料) メンバーシップ校の方800円(入館は無料) 開催日詳細は、予約サイトまたはカレンダーをご覧ください  予約優先制ですが、定員に達していない時間帯であれば予約なしで受付可能です |
主な展示作品

青磁輪花茶碗 銘 馬蝗絆
東京国立博物館蔵
Image: TNM Image Archives
(展示期間:Ⅰ期)

東京国立博物館蔵
Image: TNM Image Archives
(展示期間:通期)

野村美術館蔵
(展示期間:Ⅰ期)
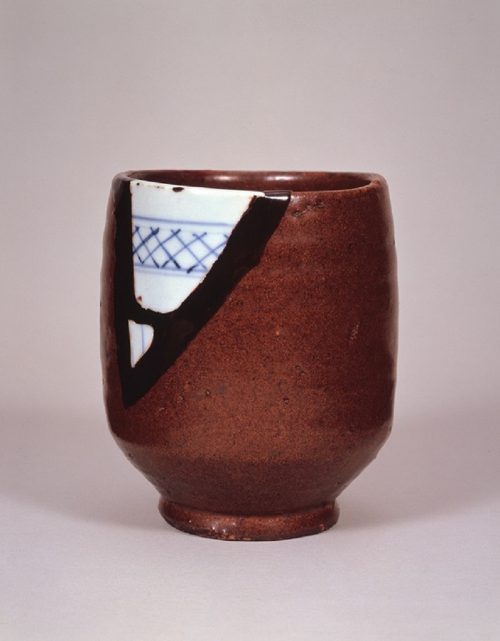
永青文庫蔵
(展示期間:Ⅰ期)
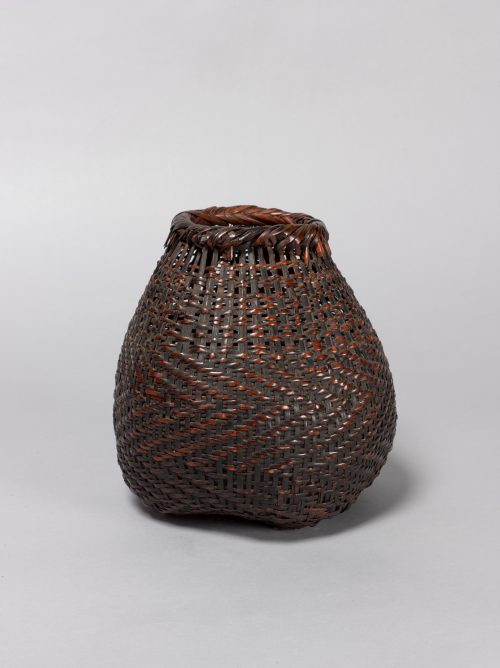
香雪美術館蔵
(展示期間:Ⅱ期)

相国寺蔵
(展示期間:Ⅲ期)
関連イベント
【金継ぎワークショップ】
日にち:9月27日(土)・28日(日)
講 師:島本恵未氏(蒔絵師/表望堂代表)
会 場:茶道資料館1階

① 和菓子の金継ぎ(呈茶付)
時 間:各日❶10:00~ ❷11:15~(約45分)
定 員:10名(先着順)
参加費:一人2,000円(要入館料)
申込み:こちらよりお申込みください。
※食材を使用し、漆は使用しません。(小麦・乳のアレルギー製品含む)

② 陶磁器の金継ぎ(呈茶付)
時 間:各日13:30~(約2時間)
定 員:10名(先着順)
参加費:一人8,000円(要入館料)
申込み:こちらよりお申込みください。
※金色の代用粉を使用します。
仕上げに漆を使用するためかぶれる可能性があります。
掌サイズの陶磁器の中からお好きなものをお選びいただきます。
私物の持ち込みはできません。

島本 恵未
蒔絵師/表望堂共同代表
塗師である夫・杉本晃則氏とともに、表望堂(京都市右京区)を立ち上げ、共同代表を務める。伝統工芸品から建築物の内装、最新のプロダクトまでを手掛ける。
【講演会】
令和7年秋季特別展「繕いの茶道具」の関連イベントとして、「茶道具の修復と復元」をテーマに講演会を開催します。
講師の繭山晴観堂三代目・繭山悠氏は、現在、美術古陶復元師として活躍されています。父で二代目の浩司氏とともに、東洋の古美術品を中心に独自の技術による痕跡の残らない復元を行い、これまで手掛けた作品は数千点にのぼります。
本講演会では、茶道具の修復・復元の現場や、現代の復元技術の最前線などについて、エピソードを交えながらお話しいただきます。なお、講演会開催日を含むⅢ期(11月11日~12月7日)には、悠氏が修復を手掛けた作品をあわせて展観します。現存する数多の茶道具を後世へどのように受継いでいくのか、復元師とともに考える機会といたします。
「茶道具の修復と復元」
日 時:11月15日(土)13:30~15:00
講 師:繭山悠氏(美術古陶磁復元師 繭山晴観堂)
定 員:先着85名(事前申込制)
参加費:2,500円(講演会参加者は当日入館無料)
会 場:茶道資料館1階
申込み:こちらよりお申込みください。
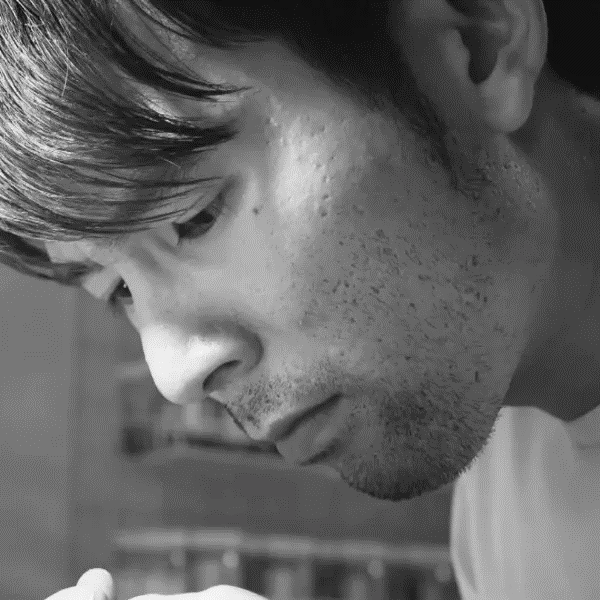
繭山 悠
美術古陶磁復元師/繭山晴観堂三代目
平成元年(1989)東京都目黒区に生まれる。
武蔵野美術大学造形学部建築学科卒業後、2011年より父・浩司の元で復元師の仕事を習い始める。東洋の古美術品を中心に作品本来の魅力を鑑賞者へ伝えるため、独自の技術による痕跡の残らない復元を行っている。
【ギャラリートーク】
担当学芸員が展示作品について解説します。※予約不要
日 時:9月18日(木)、10月24日(金)、11月23日(祝・日)
各日10:30~ / 14:30~(約30分)
参加費:無料(要入館料)
