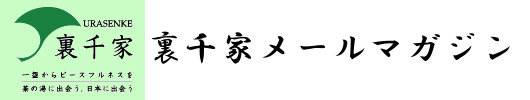 |
| 第124号(令和3年11月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『にじゅういっぷくめ』 千 宗史 若宗匠 ------------------------------------------------- |
 |
| (手なりってなんだ?) |
|
先日、あるものを食べた際にえぐみを感じました。その後間もなく、はて、えぐみってなんだ?と思った訳です。頭の中にはボヤっとしていながらも私なりの基準を持ったえぐみのイメージがあるのですが、じゃあもっと具体的に分かりやすく説明しろと言われたらできません。えぐみはえぐみでしかないのです。 ネットで辞書的な意味を調べたら「あくが強くて舌やのどがいがらっぽく感じる味」みたいな感じでした。う~ん、そう言われればそうかもしれないけど、私の頭の中のえぐみとはちょっと乖離があるような・・・。ていうか、いがらっぽいってなんだ?もっと言うならあくってなんだ? 共通認識の怪しい言葉というのはたくさんあると思います。会話をするお互いの認識が共有できていないと、場合によっては悲劇も起こりうる訳です。 皆さんの頭の中のえぐみは私の頭の中のえぐみでしょうか。辞書のえぐみと乖離していないでしょうか。 |
| ------------------------------------------------- 茶の湯の銘あれこれ ------------------------------------------------- |
| 【小倉山(おぐらやま)】 |
 |
| 秋を代表する歌枕。「雄蔵山」や「小掠山」とも記す。 京都市の北西、右京区嵯峨にある標高約286メートルのこんもりとした山。大堰川(保津川)を挟んで嵐山の向かいに位置し、古くから紅葉の名所として知られ、平安時代にはすでに貴族が行楽や隠棲の地として好んでいた。 ふもとにある天台宗の寺院・二尊院の山号は「小倉山」。二尊院の近くには、かつて藤原定家の別荘があった。定家はその邸宅の障子の装飾として、古代から鎌倉初期までの百人の歌人から一首ずつ歌を選び、年代順に色紙にしたためた。これが後に「小倉百人一首」と呼ばれる。百首の中に、紅葉をテーマとした和歌が六首あり、その一つ「小倉山 峰のもみぢ葉 心あらば いまひとたびの みゆきまたなむ」(『拾遺集』)は貞信公(藤原忠平)が詠んだ歌。 |
| ------------------------------------------------- 茶の湯トリビア ------------------------------------------------- |
| 今回は茶室・露地の分野からの出題です。茶室と露地は茶の湯を行うための空間をいい、茶の湯の進行を助けるためのさまざまな工夫がされています。 今回の問題は茶道文化検定問題集の3・4級からの出題です。 問1 茶室で、懐石や菓子を運ぶための出入口を何といいますか。(4級) ① 給仕口(きゅうじぐち) ② 躙口 (にじりぐち) ③ 茶道口(さどうぐち) ④ 貴人口(きにんぐち) 問2 千利休作と伝えられている国宝の茶室はどれですか。(3級) ① 密庵席(みったんのせき) ② 忘筌 (ぼうせん) ③ 待庵 (たいあん) ④ 又隠 (ゆういん) |
| ------------------------------------------------- 「茶の湯トリビア」解答と解説 ------------------------------------------------- |
| 問1 正解:① 給仕口 給仕口は、上部が半円形の「火灯口(かとうぐち)」を用いることが多いです。茶道口は亭主が茶を点てるために出入りする口で、給仕口と兼ねる場合もあります。 |
| 問2 正解:③ 待庵 待庵(京都府乙訓郡大山崎町・妙喜庵)は二畳の茶室です。ほかに国宝の茶室は、密庵席(大徳寺龍光院内)と如庵(犬山市有楽苑内)の2つがあります。 |