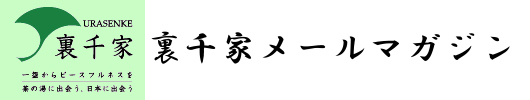 |
| 第123号(令和3年10月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『愛しきお月様』 伊住宗陽 ------------------------------------------------- |
 |
| (令和3年9月21日 唐招提寺献茶式) |
|
こんにちは! 京都は随分と朝晩冷え込むようになりましたが、皆様お住いの地域はいかがですか? 先日の唐招提寺でのお献茶式の話。 唐招提寺献茶式にお家元の名代として奉仕させていただき早、5年目。 こちらは中秋の名月にあわせて、鑑真和上とお月様にお茶をお供えいたします。 私、実はまだ一度も献茶式で満月を見ておりません。 しかし、今年はなんと!8年ぶりの中秋の名月&満月。絶好の機会到来。 御茶を供え、顔をあげると雲の波間に阻まれた月の切れ端が。 本年も満月との対面はかないませんでした。 後日聞くところによると、私が帰路についた後、満月が顔を出したそうです。 私と満月との対面はいつになるやら。 |
| ------------------------------------------------- 茶の湯の銘あれこれ ------------------------------------------------- |
| 【木守 (きまもり)】 |
 |
| 柿や柚子などを収穫する際、翌年の豊作を祈って樹木に一つだけ残す果実のこと。 利休居士は長次郎につくらせた数個の茶碗を弟子たちに分け与え、最後まで手元に残った一つの赤楽をこよなく愛し、「木守」と銘を付けたという。これは「利休七種(長次郎七種)」の一つに数えられている。官休庵に伝わり、後に高松藩主松平家に献上されたが、大正時代、東京の松平邸に保管されていたため関東大震災で破損してしまう(破片の一部を使って復元されている)。 高松市の銘菓「木守」は、この茶碗に因んで考案されたもの。干柿から作った柿餡を二枚の麩焼き煎餅で挟み、表面に焼印された渦巻きの模様は名碗「木守」の高台を模している。 |
| ------------------------------------------------- 茶の湯トリビア ------------------------------------------------- |
| 今回は茶業の分野からの出題です。茶葉は立夏の頃に摘み取られ、蒸し、乾燥、撰りなどの工程を経て茶壺に保存され、口切を迎える頃に飲用に最も適した風味となります。 問題は茶道文化検定問題集の1・2級からの出題です。 問1 世界遺産に登録されている宇治上神社(うじかみじんじゃ)に湧き出る七名水はどれですか。(2級) ① 桐原水(きりはらすい) ② 早蕨水(さわらびすい) ③ 百夜月井(ももよづきい) ④ 朝日水(あさひすい) 問2 茶園を覆う本簀(ほんず)の材料となる植物はどれですか。(1級) ① 葭 ② 麦 ③ 葦 ④ 薄 |
| ------------------------------------------------- 「茶の湯トリビア」解答と解説 ------------------------------------------------- |
| 問1 正解:① 桐原水 桐原の名は、祭神の莵道稚郎子(うじのわきいらつこ)の宮名・桐原日桁宮(きりはらひけたのみや)にちなみます。宇治七名水(桐原水・公文水(くもんすい)・阿弥陀水(あみだすい)・法華水(ほっけすい)・高浄水(こうじょうすい)・湧出水(ゆうしゅつすい)・百夜月井)のうち、現存する最後の一つです。 |
| 問2 正解:① 葭 葭簀や藁などの覆いは、一定期間、茶摘みの直前に設置され、摘む作業が終わると撤去されます。このような茶園を覆下茶園といいます。覆いをすることで柔らかく、薄く、緑の濃い新芽となります。 |