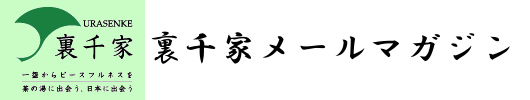 |
| 第122号(令和3年9月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『秋の訪れ』 伊住禮次朗 ------------------------------------------------- |
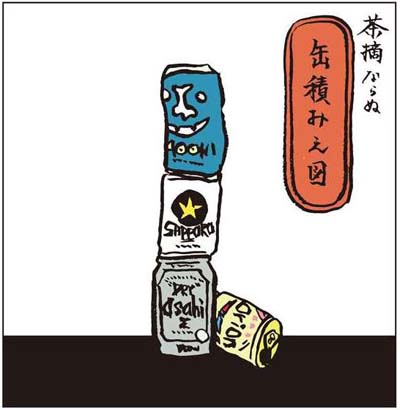 |
| (筆者挿絵:缶積みの図) |
|
パラリンピックが閉会し、新聞のテレビ欄は平時通りの様相を呈してきました。しかしながら、国内に広く緊急事態宣言が発令されている状況は続き、自粛につとめる日々はまだまだ続きそうです。今年も旅行に行けなかったなあと思いながら缶ビールを飲み、ふと空き缶に目をやると量が若干減っている――。例年、茶道資料館で秋季展のシーズンが訪れることを知らせてくれる目安です。 秋季展「新茶を祝う―製茶図と口切の茶事まで」は9月15日より開催します。茶摘みに始まる製茶の様子、そして茶壺の口切を経て我々が茶を喫するまでの流れを紹介する展示です。 茶道資料館の公式Twitter https://twitter.com/chado_shiryokan でも展覧会に関する情報を適宜更新して参りますので、是非チェックしてみてくださいね! なお、今回より挿絵も入れてみました。以降は気の向くままに… |
| ------------------------------------------------- 茶の湯の銘あれこれ ------------------------------------------------- |
| 【十六夜 (いざよひ)】 |
 |
| 月に秋草絵茶碗 |
| 秋の季語。 旧暦16日(特に8月16日)の夜。また、その夜の月のことをさす。 「ためらう」を意味する「いざよふ」の名詞で、十五夜より遅れて月が上ることをたとえた表現。「望」(満月の意)を過ぎたことから「既望(きぼう)」ともいう。 名月を鑑賞する風習は、奈良時代に中国から伝わり、詩歌管弦を伴う催しとして貴族のあいだで盛んになり、やがて武家や庶民へ広がった。中秋の名月「十五夜」(旧暦8月15日・今年は9月21日)は、里芋の収穫期にあたることから「芋名月」とも称される。御所に仕えた女官たちによって書き継がれた『御湯殿上日記』には、「名月御祝、三方に芋ばかり高盛り」とある。里芋を名月に供える慣習は今でも各地に残っており、これが月見団子の起源とされている。「十五夜」に対し、後の名月「十三夜」(旧暦9月13日)は「栗名月」などと呼ばれ、どちらか一方だけ拝むことを「片月見」と呼び、忌む慣わしがある。 |
| ------------------------------------------------- 茶の湯トリビア ------------------------------------------------- |
| 今回は茶道具の分野からの出題です。茶を点てるための道具には茶碗や湯を沸かす釜、抹茶を入れる茶入など様々なものがあり、茶席ではそれらの道具を使って客を迎えます。 問1 香を入れるための小さな蓋つきの容器を何といいますか。 (4級) ①合口(あいくち) ②香合(こうごう) ③中次(なかつぎ) ④炭箱(すみばこ) 問2 次のうち、近畿地方の焼物でないものはどれですか。(1級) ①上野焼(あがの) ②朝日焼 ③赤膚焼(あかはだ) ④膳所焼(ぜぜ) |
| ------------------------------------------------- 「茶の湯トリビア」解答と解説 ------------------------------------------------- |
| 問1 正解:②香合 茶の湯では炉の時季に練香を陶磁器の香合に、風炉の時季には香木を木地や漆器の香合に入れて使用することが慣わしとなっています。 |
| 問2 正解:①上野焼 上野焼は福岡県田川郡副智町上野で焼かれた陶器です。江戸前期の小倉藩の藩窯(はんよう)で、小堀遠州(こぼりえんしゅう)が好んだとされる七つの窯の一つです。 |
| ご不明な点は「茶道文化検定」の各級テキスト、および問題集をご覧ください。 |