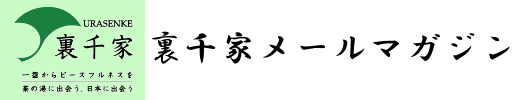 |
| 第121号(令和3年8月17日配信) |
| ------------------------------------------------- 『にじゅっぷくめ』 千 宗史 ------------------------------------------------- |
 |
|
先日、姉が第二子となる長男を出産しました。末っ子故にすべての寵愛や恩恵を我が物としてきた私に、また新たなる強力なライバルが誕生したのです。今までであればおかずの最後の1つはまず私のものでしたし、何種類かあるケーキの中から最初にチョイスする権利を有しているのもまた私でした。しかしながらさすがに今後もそういう訳にはいきません。もう31歳なのです。自分が幼い頃に見ていた大人たちはもっと優しく、立派で、大きくて。この年になっても自分はまるで追いつかないなぁと不思議に思うこともあった訳ですが、次の世代が誕生しはじめた今、やっとその理由が分かったような気がします。 少々不本意ではありますが、これからは最後の1つは姪や甥のために残しておこうと思います。 |
| ------------------------------------------------- 茶の湯の銘あれこれ ------------------------------------------------- |
| 【送り火(おくりび)】 |
 |
| 大文字送り火 2019年撮影 |
| お盆初日の「迎え火」に対して、先祖の霊を送る時に焚く火のこと。 家の前や墓地、辻や橋のたもとなどで行うものの他に、全国各地の山中や河原などで地域の行事として行われる。最も有名なものは、如意ヶ岳(京都市左京区)の「大文字」である。その由来には、平安時代初期に弘法大師・空海が飢饉や疫病の退散を念じたという説や、室町幕府八代将軍・足利義政が義尚(義政の二男)の死を悼んだとする説がある。 毎年、8月16日の午後8時から、如意ヶ岳の「大」に続いて、左京区松ヶ崎西山・東山に「妙法」、北区船山に「船」、金閣寺に隣接した左大文字山に「左大文字」、右京区曼荼羅山に「鳥居」が順に点火される。無病息災や厄除けを祈って、送り火を盃などに映して飲んだり、火床に燃え残った炭を白地に包んで戸口に吊るす風習がある。 ※新型コロナウイルスの影響により今年の五山送り火は規模を縮小しての実施が予定されています。 |
| ------------------------------------------------- 茶の湯トリビア ------------------------------------------------- |
| 今回は茶のこころの分野からの出題です。茶道は禅の教えと結びつき、茶を飲むことで禅の心を養うことが大切であると教え伝えられてきました。 出題は『茶道文化検定』問題集の3級からです。 問1 逸話で、千利休が茶室の中ではすべての人が平等であるということを実践したのは誰に対してですか。(3級) ①銭屋宗納(ぜにやそうのう) ②豊臣秀吉(とよとみひでよし) ③木村常陸介(きむらひたちのすけ) ④津田宗及(つだそうぎゅう) 問2 夏越の祓(なごしのはらえ)のとき、神社の入口でくぐるものは何ですか。(3級) ①鳥居 ②しめ縄 ③茅の輪(ちのわ) ④のれん |
| ------------------------------------------------- 「茶の湯トリビア」解答と解説 ------------------------------------------------- |
| 問1 正解:③木村常陸介 利休が堺の町人銭屋宗納を正客として茶会を行っていたところ、豊臣秀吉の家臣木村常陸介がやってきて茶会に加えてほしいと頼みました。利休は正客である宗納はそのままにし、常陸介を末客として扱いました。身分制度の厳しい時代に秀吉の家臣のような人物を末席に案内することは考えられないことですが、利休は茶室の中ではすべての人が平等であることを実践していました。 |
| 問2 正解:③茅の輪 無病息災を願って、6月の末に神社では大きな茅の輪をくぐる「茅の輪くぐり」神事が行われます。 |
| ご不明な点は「茶道文化検定」の各級テキスト、および問題集をご覧ください。 |