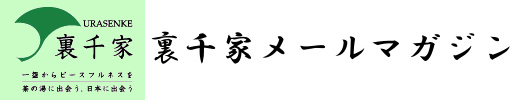 |
| 第120号(令和3年7月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『啐啄同時?!』 伊住宗陽 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:自宅の庭のブルーベリー) |
|
こんにちは!原稿を書いている今、外ではセミが心地よさそうに鳴いています。 7月のメルマガですが、先月の話を。 うちの長男が6月6日に無事、稽古始めを終えました。 親が一番冷や汗をかき緊張しながら息子の背中を見守っていたのは言うまでもありませんが、身体は元々大きい子ですがなんだかいつもより大きく見えました。 稽古始めというものは、継続して稽古をするかしないかに関わらず私は大切なものだと考えています。 親としては焦る気持ちや自分みたいになってほしい気持ちは少なからずあるかと思いますが、『啐啄同時』。彼のペースでこれからもお茶と向き合ってくれたらなと思っています。 余談ですが、稽古始め以後「お茶点ててあげよっか」と事あるごとに偉そうに言ってくる息子でした。 |
| ------------------------------------------------- 茶の湯の銘あれこれ ------------------------------------------------- |
| 【祇園会(ぎおんえ)】 |
 |
| 菊水鉾お茶席 2018年撮影 |
| 京都三大祭りの一つ、八坂神社(東山区祇園町)の祭礼「祇園祭」の正式名称。 平安時代の貞観11(869)年、神泉苑(中京区御池通大宮)に矛を立て、祇園社の神輿を運び、疫病退散を祈願したことが始まりとされる。7月1日の「吉符入り」から約1か月にわたり、八坂神社や氏子町で諸行事が行なわれる。祭のハイライト「山鉾巡行」は本来、神輿渡御(とぎょ)に伴う露払いに位置付けられていたが、時代と共に町衆の力によって発展。それぞれに趣向が凝らされた絢爛豪華な山鉾は「動く美術館」と称され、国の重要無形民俗文化財に指定(1979)、ユネスコの無形文化遺産に登録(2007)されている。 山鉾の一つ・菊水鉾(下京区室町通四条上る)では毎年、13日から16日まで会所に各流派の茶席が設けられる。町内には、かつて名水「菊水之井」があり、これが鉾の名の由来となった。室町時代後期、堺から上洛した武野紹鷗(1502~55)が邸宅「大黒庵」を構えた地としても知られている。 ※山鉾巡行は新型コロナウイルスの影響により昨年に続いて中止。 |
| ------------------------------------------------- 茶の湯トリビア ------------------------------------------------- |
| 今回は懐石の分野からの出題です。懐石の料理は一汁二菜か三菜がよいとされ、質素であることを旨としていました。 出題は『茶道文化検定』問題集の1・2級からです。 問1 小吸物(こずいもの)の別名は何ですか。(2級) ①湯次(ゆつぎ) ②銚子(ちょうし) ③盃(さかずき) ④箸洗(はしあらい) 問2 はじめて「懐石」という言葉を用いた茶書は次のうちどれですか。(2級) ①「松屋会記(まつやかいき)」 ②「鳥鼠集四巻書(うそしゅうよんかんしょ)」 ③「利休百会記(りきゅうひゃっかいき)」 ④「南方録(なんぽうろく)」 |
| ------------------------------------------------- 「茶の湯トリビア」解答と解説 ------------------------------------------------- |
| 問1 正解:④箸洗 小吸物はかすかな味をつけた吸物です。箸先を洗い清める意味があることから、箸洗とも称されます。 |
| 問2 正解:④「南方録」 茶会の食事を「懐石」というようになったのは、江戸時代中期の書である立花実山(たちばなじつざん)の「南方録」からです。 |
| ご不明な点は「茶道文化検定」の各級テキスト、および問題集をご覧ください。 |