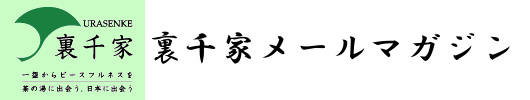 |
| 第118号(令和3年5月17日配信) |
| ------------------------------------------------- 『じゅうきゅうふくめ』 千 宗史 ------------------------------------------------- |
 |
|
楽しかったゴールデンウィークと言いたいところですが、京都は目下緊急事態宣言中。正直、こう何度も発令されると状況に慣れてしまって気が緩んでしまいそうなところですが、そこをなんとかもうひとふんばりしていきましょう。 外出に気を使うようになって久しい訳ですが、私は元来どちらかというとインドアな人間です。別に外が嫌いな訳ではありません。ちょっとした覚悟と決意を持たねば家から出る気が起きないのです。元々そういうタチだったのがこのコロナ禍で拍車が掛かり、余計出不精になってしまいました。何でも室内で完結させられる今の時代が悪いんだ。いや、どう考えても悪いのは家に引きこもる私です。気付けばお腹も少し出てきました。万全のコロナ対策をして散歩にでも行くべきでしょうか。 |
| ------------------------------------------------- 茶の湯の銘あれこれ ------------------------------------------------- |
| 【薫 風 (くんぷう)】 |
 |
| 夏の季語。 野山や木立などを抜け、若葉の香りを運ぶ穏やかな風のこと。茶席では掛物や茶杓の銘によく使われる。古くは、花の香りを運ぶ南風のことを広く指したが、江戸時代以降、俳諧の影響を受けて初夏を表す言葉に定着していった。「風薫る」という読み方もあり、5月を形容する枕詞として使われる。 そもそもの由来は、唐の文宗皇帝の側近・柳公権が皇帝とのやり取りの中で詠んだ「薫風自南来(くんぷうじなんらい) 殿閣生微凉(でんかくびりょうをしょうず)」という句にある。これを宋代の禅僧・圜悟克勤(えんごこくぐん)が説法に取り上げたことから、禅語として広く知られるようになった。文人官僚だった柳公権は書に長け、力強く美しい書風で一家を成し、その字体は「柳体」と称される。 |
| ------------------------------------------------- 茶の湯トリビア ------------------------------------------------- |
| 今回は茶事・茶会の分野からの出題です。茶の湯の目的は、茶事・茶会によって人と人とが集い、茶を喫し、料理を食して一時を楽しむ、ということがあります。 出題は『茶道文化検定』問題集の1・2級からです。 問1 茶事に招かれた客は、茶事前日に亭主宅へ出向き、招かれた御礼の挨拶をします。これを何といいますか。(2級) ①御礼 ②前礼(ぜんれい) ③後礼(ごれい) ④先礼(せんれい) 問2 席中に半東が控えて、亭主と客の間を取り持つことが必要な茶事はどれですか。 (1級) ①飯後(はんご)の茶事 ②一客一亭(いっきゃくいってい)の茶事 ③立礼(りゅうれい)の茶事 ④夜咄(よばなし)の茶事 |
| ------------------------------------------------- 「茶の湯トリビア」解答と解説 ------------------------------------------------- |
| 問1 正解:②前礼 茶事に招かれた時は、当日の二、三日前までには返事が届くように返信を出します。丁寧にするには、茶事の前日に亭主宅に出向き、御礼のあいさつをします。これを前礼といいます。 |
| 問2 正解:③立礼の茶事 立礼席では客は円椅(えんい)【椅子】に座りますが、その前に喫架(きっか)【机】があるので席から前に出ることが困難であるため、席中に控えた半東がお茶や道具の取り次ぎを行います。 |
| ご不明な点は「茶道文化検定」の各級テキスト、および問題集をご覧ください。 |