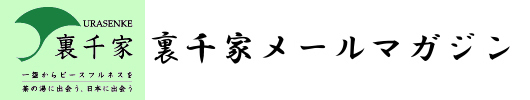 |
| 第117号(令和3年4月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『春のひととき』 伊住宗陽 ------------------------------------------------- |
 |
|
こんにちは! 4月に入り随分と暖かくなり、家の庭に植えている木蓮が一斉に花開きました。 なんだか庭が華やいで、毎日心地よいです。 先日、庭で子どもたちが騒いでいるので何かと思ったら、家庭菜園に変な虫がいると大はしゃぎ。 ぱっと見てもなんの虫かわからず、、、そんな時に写真を撮ったらなんという名前の虫か自動で判定してくれるアプリがあると知り!すぐダウンロードして写真を撮りましたら、「ガガンボ」という虫だと判明しました。 便利なアプリがあるなぁと一人で感心しつつ、気づくと横で息子が昆虫図鑑を見ていました。 なんだか、不甲斐ない気持ちになった春の土曜日でした。 |
| ------------------------------------------------- 茶の湯の銘あれこれ ------------------------------------------------- |
| 【花筏(はないかだ)】 |
 |
| 春の季語。 花びらが水面を流れる様子を筏にたとえた言葉。桜花と折枝、流水を配した花筏の文様は、春を代表する意匠として着物や蒔絵・色絵の図柄によく用いられる。高台寺(京都市東山区)の霊屋(おたまや)と呼ばれる秀吉と北政所の霊廟(重文)には、菊桐や花筏、楽器などの優美な蒔絵が施されており、これらを総称して「高台寺蒔絵」という。茶道具では炉縁をはじめ、棗や手桶水指、茶碗などにあしらわれる。 植物のハナイカダは北海道西南部から九州にかけて分布するミズキ科の落葉低木。葉の中央に淡い緑色をした粒状の花が咲くことから、「嫁の涙」や「飯(まま)っ子」などの別名があり、山菜として若葉を食用にする地域もある。 |
| ------------------------------------------------- 茶の湯トリビア ------------------------------------------------- |
| 今回は茶道具の分野からの出題です。喫茶が始まった頃は、唐物(中国製)が使われていましたが、茶の湯の発展にともない和物(日本製)の道具なども取り合わせられるようになりました。 出題は『茶道文化検定』問題集の4・3級からです。 問1 掛物の中で、手紙のことは何といいますか。(4級) ①墨跡(ぼくせき) ②画賛(がさん) ③絵画(かいが) ④消息(しょうそく) 問2 高麗茶碗の一つである「御本」は何と読みますか。 (3級) ①おもと ②おんほん ③ごほん ④ぎょもと |
| ------------------------------------------------- 「茶の湯トリビア」解答と解説 ------------------------------------------------- |
| 問1 正解:④消息 消息とは手紙のことで、「文(ふみ)」ともいいます。掛物として使用する場合、茶に関係する内容のものが特によろこばれます。 |
| 問2 正解:③ごほん 高麗茶碗は、わび茶の隆盛とともにわび茶にかなう茶碗としてもてはやされるようになります。御本は日本からの注文によってつくられたものです。 |
| ご不明な点は「茶道文化検定」の各級テキスト、および問題集をご覧ください。 |