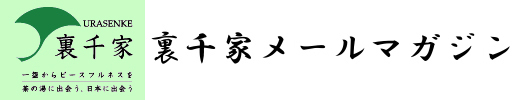 |
| 第116号(令和3年3月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『淡交での連載がスタート』 伊住禮次朗 ------------------------------------------------- |
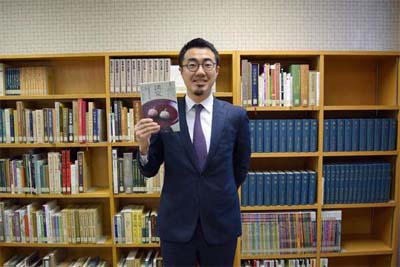 |
| (写真:今日庵文庫にて) |
|
こんにちは。穏やかな気候に恵まれる日が少しずつ増えてきたように思いますが、いかがお過ごしでしょうか。私はというと、本年1月より『淡交』で初めての連載が始まり、毎月の原稿締め切りに追われる日々を過ごしております。 「釜と鋳物師」と題して、茶の湯釜に関連する産地を毎号取り上げていく連載です。タイトルからお察しの通り、読み易い内容とは言えません。読者の皆さまには、なんというカタイ文章であることか、とスルーされるのではないかと懸念しました。そこで、少しは目に留まる連載にしたいと思い、挿絵を入れることにして今に至ります。それ自体は悪くないアイデアだったと思うのですが、原稿にあわせて毎月挿絵も描かなあかん…ということで、既にヤッチマッタ感を抱いております。 |
| ------------------------------------------------- 茶の湯の銘あれこれ ------------------------------------------------- |
| 【西王母(せいおうぼ)】 |
 |
| 中国古代の神話や伝説に現れる女神の名。 同国最古の地理書『山海経(せんがいきょう)』には、疫病と刑罰を司る神として、豹の尾と虎の牙を持つ半人半獣の姿で描かれている。後に神仙思想と結びついて不老不死の象徴となり、東王父と対をなす神として信仰され、美しい仙女の姿へ変化していく。西方にそびえる崑崙山(こんろんざん)に住み、庭に三千年に一度実のなる桃の木があり、その実を食べると永遠に年をとらないとされた。長寿を願った前漢の武帝に仙桃を授けた伝説が残る。後漢末に道教が成立すると、全ての仙女の長として最高位に位置付けられた。 日本では能の演目や近松門左衛門作の浄瑠璃「日本西王母」があり、茶の湯では桃の代名詞として菓子の銘などに用いられる。 |
| ------------------------------------------------- 茶の湯トリビア ------------------------------------------------- |
| 今回は茶の歴史の分野から、茶の湯(喫茶)に関わった人物についての問題です。中国で仏教を学んだ留学僧たちが茶を飲む習慣を伝え、日本の美意識の中で茶の湯は多様に変化していきました。 出題は『茶道文化検定』問題集の2・3級からです。 問1 江戸時代初期、飛騨(ひだ)(岐阜県)の大名の子として生まれながら、京都の公家などに自らの茶を伝えた人物は誰ですか。 (3級) ①加藤忠広(かとうただひろ) ②金森宗和(かなもりそうわ) ③古田織部(ふるたおりべ) ④片桐石州(かたぎりせきしゅう) 問2 中国・北宋(ほくそう)の皇帝で『大観(だいかん)茶論(ちゃろん)』を著した人はだれですか。(2級) ①神宗(しんそう) ②仁宗(じんそう) ③徽宗(きそう) ④穆宗(ぼくそう) |
| ------------------------------------------------- 「茶の湯トリビア」解答と解説 ------------------------------------------------- |
| 問1 正解:②金森宗和 金森宗和は、飛騨(岐阜県)の大名の子でしたが、京都に出て主に公家などに自らの茶を伝え、「姫宗和(ひめそうわ)」といわれる独自のスタイルを作り出しました。また、仁和寺(にんなじ)門前に窯を築いた仁清(にんせい)に作陶を指導しました。 |
| 問2 正解:③徽宗 中国・北宋の八代皇帝徽宗は、『大観茶論』を著し、「静面点(せいめんてん)」などの点茶法を紹介するなど茶に関心が高い人物でした。 |
| ご不明な点は「茶道文化検定」の各級テキスト、および問題集をご覧ください。 |