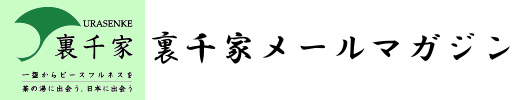 |
| 戞114崋乮椷榓3擭1寧15擔攝怣乯 |
| ------------------------------------------------- 亀怴擭偛垾嶢亁丂埳廧廆梲 ------------------------------------------------- |
 |
|
丂擔崰傛傝乽棤愮壠儊乕儖儅僈僕儞乿傪偛垽撉偄偨偩偒丄桳傝擄偆偛偞偄傑偡丅 丂怴宆僐儘僫僂僀儖僗姶愼徢偺慡崙揑側奼戝偵傛傝拞乆丄奆條偲偍夛偄偡傞婡夛偲偄偆傕偺偑側偔丄庘偟偄偐偓傝偱偡丅 丂儊乕儖儅僈僕儞偱偼偦偺暘丄堦曽捠峴偱偼偁傝傑偡偑丄廆巎庒廆彔傪昅摢偵釾師楴丄巹偺庒庤3恖偑敪怣偡傞桞堦偺応偱偡偺偱丄崱擭傕憡曄傢傝傑偣偢偍晅偒崌偄偔偩偝偄丅 丂杮擭傕乽棤愮壠儊乕儖儅僈僕儞乿傪壗懖媂偟偔偍婅偄抳偟傑偡丅 |
| ------------------------------------------------- 亂怴楢嵹亃 拑偺搾偺柫偁傟偙傟 ------------------------------------------------- |
| 傢偐傒偢亂庒悈亃 |
 |
| 幨恀丗崱擔埩乽攡偺堜乿偺庒悈壉乮1寧7擔乯 |
| 怴擭偺婫岅丅乽堜壺悈(偣偄偐偡偄)乿偲傕偄偆丅屆偔偼丄媨拞偱棫弔偺擔偺憗挬偵堜屗偐傜媯傫偱揤峜傊曭偠偨悈傪巜偟丄屻悽偵側偭偰尦扷偺挬偵媯傓悈偺偙偲傪巜偡傛偆偵側偭偨丅怴偟偄壉傗暱庅傪巊偆偺偑廗傢偟偱丄幾婥傪暐偄丄柍昦懅嵭丒庒曉傝偺岠梡偑偁傞偲偝傟丄恄慜偵嫙偊傞傎偐丄庤悈傗堸梡丄椏棟偺幭悊偒梡偲側傞丅棤愮壠偱偼乽攡偺堜乿偐傜媯傫偩庒悈偑擭弶偺乽戝暉拑乿偱梡偄傜傟傞丅亀撿曽榐亁偵偼丄乽堿(偄傫)乿偱偁傞栭偺悈偑惗婥傪幐偆偺偵懳偟丄乽梲(傛偆)乿偺偼偠傑傝偵偁偨傞柧偗曽(撔偺崗)偺悈偼惔傜偐偱惗婥偵偁傆傟偰偄傞偨傔丄拑帠丒拑夛偱偼忢偵乽憗挬偵媯傫偩悈傪梡偄傞偙偲偑拑偺搾幰偺怱峔偊乿偱偁傞偲愢偐傟偰偄傞丅 |
| ------------------------------------------------- 拑偺搾僩儕價傾 ------------------------------------------------- |
| 丂崱夞偼壻巕偵偮偄偰偺弌戣偱偡丅婫愡偺堏傝曄傢傝偑偼偭偒傝偟偨擔杮偱偼丄愜乆偺晽暔傪岻傒偵幨偟庢偭偰偨偔偝傫偺偍壻巕偑嶌傜傟傑偟偨丅 丂弌戣偼亀拑摴暥壔専掕亁栤戣廤偺2媺丒1媺偐傜偱偡丅 栤1丂庡壻巕偺堦庬偱丄偮偔偹堭偱嶌偭偨奜旂偵镼(偁傫)傪曪傒丄忲偟偁偘偨傕偺傪壗偲偄偄傑偡偐丅(2媺) 嘆偙側偟 嘇妺壻巕(偔偢偑偟) 嘊偒傫偲傫 嘋彃錚閈摢(偠傚偆傛傑傫偠傘偆) 栤2丂乽偙側偟乿傪嶌傞偲偒偵丄偙偟镼偵壛偊傞暡偼壗偱偡偐丅乮1媺乯 嘆姦攡暡(偐傫偽偄偙) 嘇忋怴暡(偠傚偆偟傫偙) 嘊傕偪暡 嘋彫敒暡 |
| ------------------------------------------------- 乽拑偺搾僩儕價傾乿夝摎偲夝愢 ------------------------------------------------- |
| 丂栤1丂惓夝丗嘋彃錚閈摢 丂偮偔偹堭偺敀偄晹暘傪偡傝偍傠偟丄嵒摐傪壛偊偰傛偔崿偤崌傢偣丄忋梡暡傪壛偊偰楙偭偨傕偺偱镼傪曪傒丄忲偟婍偱忲偟傑偡丅楩偺婫愡偵懡偔巊傢傟傞偍壻巕偱偡丅 |
| 丂栤2丂惓夝丗嘋彫敒暡 丂忋壻巕偵摿桳偺庬(偨偹)偺偆偪丄尒偨栚偼帡偰偄傑偡偑乽楖(偹)傝偒傝乿偲乽偙側偟乿偑偁傝傑偡丅乽楖傝偒傝乿偼偙偟镼偵姦攡暡傪楙傝偙傫偩傝丄偓傘偆傂偱偮側偄偱楙傝忋偘偨傕偺丅乽偙側偟乿偼丄偙偟镼偵彫敒暡傪壛偊偰忲偟偰偐傜傕傒偙傫偩惗抧偱偡丅 |
| 丂偛晄柧側揰偼乽拑摴暥壔専掕乿偺奺媺僥僉僗僩丄偍傛傃栤戣廤傪偛棗偔偩偝偄丅 |