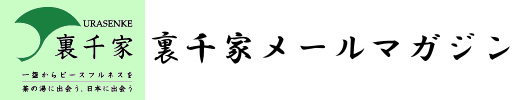 |
| 第113号(令和2年12月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『裏千家学園の公開授業を終えて』 伊住禮次朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:裏千家学園茶道専門学校公開授業にて) |
|
裏千家学園では、これまで年に一度の公開講座を行っておりました。しかしながら、本年は新型コロナウイルス感染症拡大を鑑み、初めての試みとしてZoomを用いたオンラインでの公開授業の形式で開催いたしました。 タイトルは「温故知新―近代の茶の湯と各服点再興―」。近代における茶の湯の展開と、裏千家十三代円能斎が考案された各服点がテーマでした。第1部は、熊倉功夫氏(MIHO MUSEUM館長)の講義「近代の茶の湯」。第2部は筒井紘一氏(茶道資料館顧問)を交えての対談で、私は司会進行をつとめました。 対談では、濃茶の飲み回しに関する歴史に始まり、衛生観念の高まりと共に人びとの意識はどのように変化したのかなどが論題となりました。現代への提言を含む両氏の対談を間近に拝聴し、学び多き時間でした。 |
| ------------------------------------------------- 茶の湯トリビア ------------------------------------------------- |
| 今回は茶室についての出題です。茶室は茶の湯を行うことを目的として建てられた施設です。 出題は『茶道文化検定』問題集の4級・3級からです。 問1 国宝の茶室ではないものはどれですか。 (4級) ①待庵(たいあん) ②如庵(じょあん) ③又隠(ゆういん) ④密庵席(みったんのせき) 問2 初期の茶の湯空間は、和歌や連歌、生け花などの文芸・遊芸も楽しむ社交のための建築であり、舶来品(唐物)などが飾られていました。そのような建築物を何といいますか。(3級) ①詰所 ②合所 ③集所 ④会所 |
| ------------------------------------------------- 「茶の湯トリビア」解答と解説 ------------------------------------------------- |
| 問1 正解:③又隠 国宝の茶室は待庵、如庵、密庵席の3つです。又隠は裏千家家元にある重要文化財の茶室です。 |
| 問2 正解:④会所 初期の茶の湯空間の起こりは、文芸・遊芸を中心とする社交の建築である「会所」に見られます。さらに、会所の飾りつけの場が洗練され、床の間、違棚(ちがいだな)、付書院(つけしょいん)がそなえつけられ、畳が敷き詰められるなどして「書院造(しょいんづくり)」が確立します。 |
| ご不明な点は「茶道文化検定」の各級テキスト、および問題集をご覧ください。 |