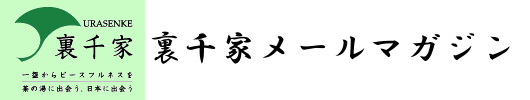 |
| 第105号(令和2年4月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『私たちにできる事』 伊住 宗陽 ------------------------------------------------- |
 |
|
こんにちは! 日本も含めて今世界中を新型コロナウイルスが席巻しています。 たった数か月でここまで日常が変わるものかと驚くばかりです。 裏千家としてもお茶会、献茶式、地区大会、青年部全国大会と軒並み中止もしくは延期を余儀なくされております。 人と人との交流が制限され、一碗のお茶も共有できない寂しさをしみじみと感じています。 でも、こういう暗く言いようのない閉塞感のトンネルを抜けた先に、必ず茶道を求める方が大勢いらっしゃる。そう信じて、不要不急の外出を控え、家で書物から知識を得る時間を確保してみる、基本の割り稽古などで自己の研鑽に努める等。それが我々茶人としての今できる事かなと思います。 皆様とまた茶の湯を通した交流を深められる日を心待ちにしています。 |
| ------------------------------------------------- 茶の湯トリビア ------------------------------------------------- |
| 今回は3級と4級の茶道具からの出題です。3級は少しお茶の稽古に慣れた中級者になりかけた方を対象にしています。4級は初心者を対象とした、いわば入門編です。ただし、例外もありますのでここに載せた解答はあくまで基本です。出題は『茶道文化検定』3級、4級のテキスト、ないし同問題集からです。 問1 花入を畳床に置くとき、下に敷く板を何といいますか。(3級) ①敷瓦(しきがわら) ②花敷(はなしき) ③薄板(うすいた) ④置板(おきいた) 問2 茶入を入れる袋を何といいますか。(4級) ①帛紗(ふくさ) ②仕覆(しふく) ③包袋(つつみふくろ) ④袋物(ふくろもの) |
| ------------------------------------------------- 「茶の湯トリビア」解答と解説 ------------------------------------------------- |
| 問1 解答:③薄板 茶席では季節の花が花入(はないれ)に入れられます。その花入は主に床の間に置かれます。床の間の畳の上に花入を置くときには、原則として畳を傷めないために薄板というものを敷きます。板には漆塗りのもの、何も塗らない木地の板の二種類があります。形状も二種類に分かれますが、それぞれ花入の種類によって使い分けられます。 |
| 問2 解答:②仕覆 席で使う抹茶には、濃茶と薄茶があります。このうち濃茶をいれる小さな陶器製の壺を茶入(ちゃいれ)といいます。茶入は金襴(きんらん)などの高級な裂地(きれじ=織物)で作られた仕覆に入れて用います。仕覆とは茶入を包む袋のことで、いかに茶入が大切に扱われていたかがわかります。仕覆には別に取り扱い方が決められています。 |
| ご不明な点は「茶道文化検定」の各級テキスト、および問題集をご覧ください。 |