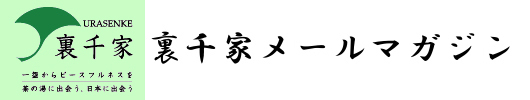 |
| 第99号(令和元年10月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『今日庵文庫と茶道資料館』 伊住禮次朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:茶道資料館にて) |
|
本年は、茶道資料館開館40周年、今日庵文庫開館50周年を迎える節目の年です。機関としてはじめに開設されたのは今日庵文庫。11代玄々斎が蔵書整理をされたことに始まります。玄々斎は、その蔵書群を「玄々文庫」や「今日庵文庫」と称しました。 時代は下って、昭和44年には鵬雲斎大宗匠が、茶の湯関係資料の蒐集及び保存、調査研究を目的とした茶の湯の専門図書館「今日庵文庫」を開設。そして、昭和54年には研究成果の発信や、茶道美術の展示公開、普及活動の実践を行うものとして博物館法に基づく「茶道資料館」の開館を迎えます。 時折、淡交会会員でないと利用できないのかという問い合わせをいただきますが、言うまでもなく、いずれも茶道経験の有無や流儀を問わずご利用いただける施設です!これからの時代も裏千家における「学」の拠点として、先人の思いをしっかりと受け継いでいけるように精進してまいります。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:原 三渓 ------------------------------------------------- |
| 原 三渓については、6月の益田多喜子の項で名前だけ出ましたが、本名は富太郎。岐阜県の出身で、東京専門学校(早稲田大学の前身)卒業後、横浜の生糸貿易商 原 善三郎の婿養子となります。三渓は、原商店の近代化に成功し、帝国蚕糸会社社長のほか、多数の銀行・会社の重役を兼任し、横浜随一の財閥に育て上げました。また、本牧三ノ谷海岸の広大な土地に庭園を設けて三渓園と名付け、室町から江戸時代の建物を移築し、一般に公開しました。美術品の収集につとめ、多くの日本画家を育成したことでも知られています。 夏になると三渓園の庭の大池一面に見事な蓮の花が咲きます。三渓は朝茶の懐石に、浄土飯(じょうどはん)と称する蓮の実飯を作って連客をもてなしたそうです。これは、飯櫃(びつ)に蓮の青葉を拡げて白米飯を盛り、飯上に紅蓮弁を覆うことで一見大輪の蓮華のようにしたもの。それを各自に盛り分けて、半熟の柔らかい蓮の実の丸煮を振りかけ、その上にだし汁を掛けただけのものでしたが、この飯を飲み下した時の香気と渋味はえもいわれぬものだったとか。客は何杯も食べたそうです。これは食通の三渓が考案したものでしたが、鈍翁や松永耳庵に深い感動を与えたとのことです。 |