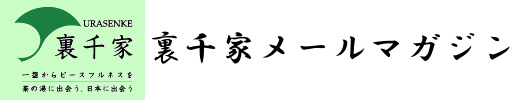 |
| 第97号(令和元年8月19日配信) |
| ------------------------------------------------- 『夏の思い出』 伊住 宗陽 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:祇園祭にて) |
|
こんにちは! 今年も暑い夏がやってまいりましたね。 皆さま如何お過ごしでしょうか? さて、少し前ですが祇園祭山鉾巡行のボランティアを裏千家職員有志、学園生・みどり会有志と共に今年も無事に終える事ができました。 私は初めて旗持ちという行列の先頭を務めさせていただきました。 応援団ばりの旗を掲げてゆっくりと行列をリードしなければいけない重要な役です。 しかし、事件が。 旗を装着する腰ベルトが、、、日頃の不摂生により締まらず、、、 両腕の力だけで旗をもち、気力でなんとか歩ききりました。翌日は見事に両腕筋肉痛になったのは言うまでもありません。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:戸田露朝 ------------------------------------------------- |
| 大阪の茶道具商谷松屋(たにまつや)は、歴代道具の目利きがその当主となり、今に至っています。文化5年(1808)には松平不昧が谷松屋を訪れ、「一玄庵」の庵号を授け、自らその扁額を揮毫しているほどです。この谷松屋の九代目が戸田露朝(ろちょう)、通称弥七でした。露朝は明治後半から昭和の初期まで活躍しましたが、それは先代の露吟(ろぎん)の厳格な訓練を受け、道具の鑑定に秀でていたからです。露朝は大正6年(1917)希代の道具収集家であった赤星弥之助家の所蔵品売立ての際、一手に数十万円(現在の数十億円)の名品を取り扱いました。また同12年の小浜酒井家所蔵品売却時には、のちに米国・ボストン美術館に収められ文化財の海外流出と大騒動になった「吉備大臣入唐絵巻」を18万円で落札するなど数々の名品を引き受けて、当時の茶道具商界の第一人者と目され、顧客には平瀬露香・藤田香雪・益田鈍翁などがいました。 さてこの露朝、臨終にあたり、辞世を書くからと筆紙を持ってこさせ、「そろばんのたまにうまれし人の世につまり八八の六十四年」という狂歌と、「大笑ひハッハ六十四(し)出(で)の旅」という狂句を残して3時間後に大往生しました。 |