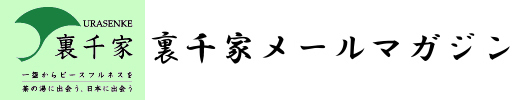 |
| 第96号(令和元年7月16日配信) |
| ------------------------------------------------- 『貴船神社の水まつり』 伊住禮次朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:貴船神社献茶式にて) |
|
7月8日、貴船神社の水まつりにおきまして、謹んで献茶式をご奉仕させていただきました。私にとっては初めての献茶奉仕となりました。ご列席の上、共にご参拝いただきました皆様、まことにありがとうございました。 生前には父・宗晃もご奉仕させていただいておりました貴船神社の献茶式、感慨深いものがございます。釜を懸けていただいたのは京都東支部、京都南支部の皆様でした。副席の「ふじや」さんでは、父の作った茶杓が登場。珠光作の竹茶杓「茶瓢」(香雪美術館蔵)を蟻腰にしたような大変面白い造形で、興味深く拝見いたしました。また、本席は馴染み深い「ひろや」さん。茶席を設けるのは本年最後とのことで、在釜の風景を目に焼き付けるようにのぞんだ思い出深い一席となりました。 貴船神社の水まつりは、雨乞い神事に由来するといいます。言うまでもなく土地を豊かにする降雨ですが、今年も各地で豪雨被害が出ており心苦しい限りです。どなた様にとっても、健やかで心穏やかな日々が訪れることを祈念しております。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:森川如春庵 ------------------------------------------------- |
| 今までご紹介した数寄者たちは、その出身はともかく、活躍した場所は東京・大阪などでした。今回は「茶人の逸話」名古屋に出張し、尾張の茶人如春庵(じょしゅんあん)森川勘一郎が登場します。 如春庵は愛知県一宮市の富農に生まれ、17歳の時に大阪平瀬家の入札会で、光悦作「乙御前(おとごぜ)」茶碗を落札したことで、その名を上げました。その如春庵が名古屋市に新たに移築した田舎家(いなかや)を舞台に茶会を開いたのが昭和4年3月のこと。当時の数寄者の間では、心の健康は農村にあるということで、茶の湯の場として田舎家を持つことが流行っていたのです。 如春庵の田舎家は、益田鈍翁も感服して、同家訪問名簿に「小作人 鈍翁」と署名したほどの天下一の田舎家。如春庵は高橋箒庵と名古屋の道具商横井庄太郎を客として招き、炉に囲炉裏を用い、麻縄の自在で「羽釜」を天井の梁から釣り下げるという豪快さ。懐石は炉に掛かった釜から飯をつぎ、汁を出し、客が手盛りするに任せ、勝手に食べるという趣向。いかにも田舎家らしいものでした。この建物、11歳の如春庵が気に入り、後に売られましたが、買値の2倍を払い入手したものでした。 |