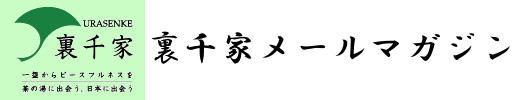 |
| 第95号(令和元年6月17日配信) |
| ------------------------------------------------- 『じゅうにふくめ』 千 敬史 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:南紀支部・青年部創立50周年記念大会にて) |
|
なんだか梅雨の時期にメルマガ原稿を書くことが多いなぁと思っていたんです。ふと気が付きましたが、私含め3人で回しているので毎年同じ月の担当になるのは当たり前のことでした。むし暑くなってきましたが皆さん如何お過ごしでしょうか。 今年は冷夏になる可能性があると言われています。寒いのは着込めばなんとかなっても暑いのはどうにもならないので個人的には有難いことですが、近年は気温変動が極端で春と秋の丁度良い気候が減りつつあるような気がします。個人レベルではどうしようもないことかもしれませんが、「四季」が「二季」とならぬような未来を願いたいものですね。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:益田無塵庵 ------------------------------------------------- |
| 明治以降、茶の湯を担った数寄者たちですが、その夫人たちも茶の湯をたしなみ、やがては自ら茶道具を買い求め、茶会を開くような女流茶人が現れるようになりました。その代表的な一人が益田鈍翁の側室、益田多喜子こと益田無塵庵(むじんあん)でした。 昭和3年(1928)11月、多喜子は昭和天皇の即位礼と自らの還暦の祝賀を兼ねて、関東大震災後の仮の住まいであった芝区(現港区)下高輪の東禅寺庵室に、横浜の貿易商で数寄者の原三渓夫妻、高橋箒庵などの客の外に半東をつとめる鈍翁などを招き入れました。茶室の掛物は優美な絵掛物を使い、炭手前の際の交趾香合も釉色見事なもの。中立後の席入りでは、銅鑼を一つ打ち残し、多喜子自ら出迎えるという趣向。濃茶席では鈍翁より還暦祝いとして贈られた松花堂所持の八幡名物(やわためいぶつ)「唐物奈良文琳」、茶碗は同じく八幡名物の高麗茶碗「白鷗」という八幡名物揃いの道具組に客たちは感心しきり。多喜子は目から鼻に抜けるような才女といわれ、出入りする財界人から得た情報で利殖し、道具の目利きにもたけ、すぐれた道具を所蔵し、鈍翁の影響もあって稀代の女流茶人となりました。 |