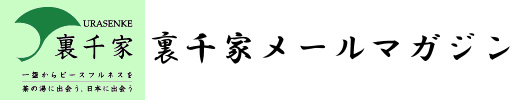 |
| 第93号(平成31年4月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『心に伝ふ』 伊住禮次朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:ジャポニスム2018の呈茶風景) |
|
肌をなでていく風が柔らかく、心地良い季節になりました。 少し前の話になりますが、本年2月、日仏交流160周年の記念行事としてパリで開催された「ジャポニスム2018」において2日間の講演と呈茶を行うため、渡仏しておりました。イベント初日はイエロージャケットによるデモと重なり、お手伝いいただく予定であったパリ協会の会員方の多くに外出を控えていただくことになり、はたして参加者はいるだろうかとさえ心配しておりましたが、その心配を一瞬で拭い去るほど多くの方にご参加いただけました。よって、初日はスタッフが一人でも欠ければ席中が滞るほど。全員が常にフル回転状態。関係各位に感謝です…! さて、海外での講演は初の試みでしたが、通訳を介した説明にはより明確に要点を伝えることが求められます。また、それに伴い思考のプロセスは変わります。呈茶では言語に依らないコミュニケーションにおける発見もありました。これらの経験を経て、茶の湯で大切なものは何かという自問自答を少しだけ深められたと感じております。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:三井泰山 ------------------------------------------------- |
| 泰山(たいざん)三井守之助は茶を好んだ三井家の中でも頭抜けた茶人でした。しかも趣向に走りがちな数寄者とは一線を画し、自らは茶の湯の王道を行くという茶風でした。 この泰山が大正9年(1920)11月、新築した東京永坂町邸(東京都港区、現在はフィリピン共和国大使館所在地)の茶室に、朝日新聞社の玄庵(げんあん)村山龍平を正客に招いて口切の茶会を開きました。茶入は中興名物古瀬戸「林肩衝」、茶碗は稲葉家伝来の「大三島」、茶杓は利休共筒と、いずれも大名道具を用い、後座の席入りには銅鑼や喚鐘などの鳴物は使わず、亭主自ら客を迎え出るという丁重さ。本格を志す亭主らしいもてなしでした。ただ初座の床に掛けられた蘭渓道隆(鎌倉時代の中頃、中国・南宋から渡来した臨済僧で、鎌倉建長寺の開山)の「細字大幅」はまさに読めない墨跡の典型だったようで、記録者の高橋箒庵も「本文ばかり25行あり」と行数だけ数えて内容には触れていません。これは中国人禅僧の墨蹟の多くが細字で書かれた長文のものが多く、茶人たちはこれが読めなかったためで、以降読みやすい一行物へと掛物の興味が移っていきました。 |