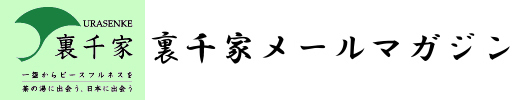 |
| 第92号(平成31年3月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『じゅういっぷくめ』 千 敬史 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:冬期講習会にて) |
|
1月の中旬に初釜が終わりました。そして今から約10ヵ月後の1月初旬に初釜が始まります。私たちが普段考えもしない暦という当たり前の概念は、気が遠くなる程の大昔では当たり前でなかったといいます。当たり前のことは当たり前なんだけど最初は当たり前ではなかった訳です。当たり前をはなから当たり前と決めつけず、そのルーツに関心を持ったり疑問を感じてみたりする、かといってしつこかったり野暮ったくないような人間でありたいと思いました。 本年度もさまざまな場所で皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。どうぞ宜しくお願い致します! |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:藤堂四州 ------------------------------------------------- |
| 能を趣向に茶会をすることは、現在でもよくあることですが、茶会の最中に能が実演されたことはあまり聞いたことがありません。それを自らの茶会で実際におこなったのが、藤堂四州(とうどうししゅう)でした。名は高紹(たかつぐ)、三重県津の藤堂家第13代で、明治23年(1890)に家督を継ぎ、伯爵となります。 大正5年3月、高橋箒庵は益田紅艶らと共に四州の茶会に招かれます。場所は東京・築地の藤堂家別邸。寄付には同家ごひいきの能楽師北七太夫の掛け軸が掛り、次に広間に移って懐石、小間の薄茶が済むと先程の広間へ再び移動。すると広間の三分の二の畳が上げられ、その下に敷舞台(仮設の能舞台)が現れています。連客一同どういう能が演じられるかと固唾をのんで見ていると、名曲「熊野(湯谷=ゆや)」が、七太夫の子孫で後に人間国宝となる14代喜多六平太によって演じられたのです。平清盛の次男、時の権力者平宗盛に翻弄される女性熊野が舞台に出現し、一同近来無類の「熊野」と感服した次第。ただ余興の紅艶の舞踊は、100㎏近い体重を本人が意識し、手加減したので床を踏み抜かなかったのは幸いと一同安堵したそうです。 |