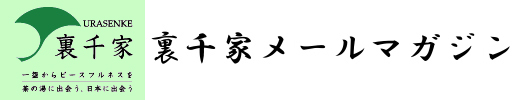 |
| 第87号(平成30年10月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『ほどほどに。』 伊住禮次朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:「さかい利晶の杜)講演会にて) |
|
こんにちは。秋の風が心地よく、涼やかな季節になりました。 先般、大阪府堺市にある「さかい利晶の杜」にて講演をさせていただいたのですが、支部の先生方をはじめ、職員の皆様にも温かく迎えていただき、秋晴れの良き一日となりました。館の開設に関わらせていただいたのが、もう3年以上も前のこと。宿院界隈に植えられたフェニックスの並木をみて、懐旧の念に浸っておりました。当日の昼食は道中で済ませたのですが、お立ち寄りになる機会がありましたら、ランチには近くの「ちく満」か「プノンペン」が私的おすすめです! あ、忘れてはならないのが、飯炊き仙人でお馴染みの「銀シャリ屋 ゲコ亭」。艶があり、ふっくらした「飯」が最高ですよ。 さて、ということで茶道資料館から特別展のご案内を。現在、秋季特別展「酒飯論絵巻−ようこそ中世日本の宴の席へ−」が開催中(12月4日まで)です。本展の中心となる「酒飯論絵巻」は、「酒」好きと「飯」好き、どちらも「ほどほど」がよしとする三者が登場し、酒と飯の良いところなどを「論」じ合う絵巻。それぞれの立場で宴を催す場面では、今も昔も変わらない人間のさまをみるようで面白い作品です。お酒もご飯もほどほどが大事なのは痛いほどに分かっている…のですが。いやはや、お察しください。上戸の方も下戸の方も、皆様のご来館をお待ちしております! |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:馬越 化生 ------------------------------------------------- |
| 馬越化生(まごしかせい)は本名恭平、流水庵と号しました。三井物産に入り、日本麦酒の再建に成功、日本麦酒が大阪麦酒(アサヒビール)・札幌麦酒(サッポロビール)などを合併してできた大日本麦酒の社長となり、日本のビール生産量の7割を同社で占め、ビール王の異名をとりました。茶の湯は鈍翁や紅艶同様、益田克徳に勧められたことによります。 化生は茶会における「感服係り」として知られ、道具を拝見するや「あっ」と感嘆の声を発するタイミングが絶妙で、また茶を飲むときも、まず茶碗を戴いて一啜りし、次に茶碗を斜め左に差出し、首をうつむけてさも意味ありげなポーズをとり、銘茶の舌にしみわたるころに舌鼓を一つ打ち、さらにこれを三回くり返したそうです。この化生の飲み方は、住まいする芝桜川町(現在の東京都港区)に因み、「桜川流」と呼ばれました。感服振りについては失敗も多く、ある時、上野の寛永寺の鐘の音を茶会の銅鑼の音と聞き間違え、「さてさてこれは名銅鑼なり」と言ったとたん、本物の銅鑼が「ボーン」と鳴り、再び音を聞くポーズをとったので、後に「二重の銅鑼聞き」と言われたそうです。 |