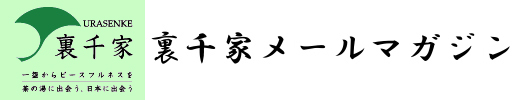 |
| 第86号(平成30年9月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『きゅうふくめ』 千 敬史 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:関東第三地区学校茶道夏期研修会にて) |
|
「梅雨を乗り切っても次訪れるは暑い夏!暑さに負けず元気にやっていきましょう」←前回私が書いたメルマガの文末ですが、夏生まれの私も今年の暑さには勝てませんでした。皆さん如何お過ごしでしょうか。 明日やろうは馬鹿野郎という言葉があります。ざっくり言うと今すぐに着手できることを先送りにするなということですが、ズバリ私のことであります。このメルマガに関しても現時点で締切直前ですし、学生時代の試験前はいつもギリギリの詰め込み学習でした。なんでも余裕を持ってやれたらなぁと思う反面、火事場の馬鹿力という言葉もあるように、追い詰められた時にこそ出る真なるパワーも馬鹿にはできません。余裕を持ちながらも真なるパワーを発揮できる渋い大人になろう。三十路前ながらにそう思った台風一過のとある日でした。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:朝吹柴庵 ------------------------------------------------- |
| 前々回登場した高橋箒庵が三井呉服店の改革にあたっていた頃、三井の同僚に朝吹柴庵(あさぶきさいあん)がいました。本名は英二、大分県出身で、福沢諭吉に可愛がられ慶応義塾を卒業後、出版部の主任となります。福沢の甥、中上川彦次郎(なかみかわひこじろう)の妹が妻でした。後に中上川が三井財閥再建のため三井に入ると、柴庵も紆余曲折の末、三井に入り、鐘ヶ淵紡績専務、三井合名工業部理事と順調に出世しました。 柴庵は、「柴庵」という茶室を持ちながら、茶会を開いたのは生涯に二度しか無かったそうです。柴庵はその客人振りと道具の鑑定に優れていたそうで、驚くべき記憶力の持ち主でした。あるとき室町三井家の当主、高保の茶会で出された宋代官窯の名品茶碗の銘を言い当て、亭主はじめ一同驚愕したということです。この茶碗は、現在東京国立博物館に所蔵される「馬蝗絆」(ばこうはん)という角倉家秘蔵の茶碗でした。また東京下谷の古書店から、徳川家が所蔵し維新の混乱時に行方不明となった「古銅青海波」の花入を、当時の金額で100円という安値で掘り出します。この花入は、先年、畠山記念館の「益田鈍翁展」に出品されていました。 |