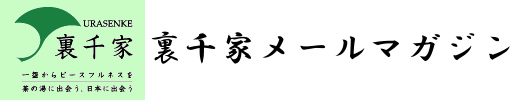 |
| 第85号(平成30年8月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『大汗』 伊住 公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:祇園祭山鉾巡行にて) |
|
京都は祇園祭も終わり、お盆に入りました。 このタイミングで旅行に行く方、故郷に帰る方、様々いらっしゃるかと思います。 私の場合、生まれてこの方、お盆中に京都を離れたことがございません。 なにが普通なのかはわかりませんが、それが当たり前と育ってきました。 13日のお盆入りから16日の送り火の日まで、毎日朝夕のお経を皆で御勤めしております。 子供の頃は父をはじめ、周りの『大人男性陣』がお経を唱えるのをじっと聞いているだけ。御勤めを終えてからいとこ達と茶の間で遊ぶというのがお盆の正しい姿でした。 しかし近年はその『大人男性陣』が少なくなり、私もお経メンバーに入らなければ成り立たなくなってきました。 私の近年の正しいお盆の過ごし方。 蒸し暑い御祖堂で大汗をかきながら、力いっぱいお経を唱える。 これぞ千家のお盆です。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:上野是庵 ------------------------------------------------- |
| 甲子園球場では高校球児の熱戦が連日繰り広げられていますが、今年は第100回の記念大会。同大会の主催者の一つ朝日新聞社には村山家と上野家という二つの社主家があります。この社主家の祖、村山龍平、上野理一の二人とも美術に造詣が深く、美術誌『国華』の有力な応援者となり、また阪神間の数寄者を集めた「十八会」を組織するなど、関西有数の数寄者でもありました。村山のコレクションは「香雪美術館」として健在です。上野理一が「是庵(ぜあん)」また「有竹斎(ゆうちくさい)」と号し、大阪市内の平野町に居を構えていた頃、茶会に益田鈍翁、高橋箒庵などを招きました。 茶室には中国の高僧竺仙梵僊の墨蹟が掛り、懐石が終わり、中立・濃茶と進み、古伊羅保の茶碗に津田宗及の茶杓、茶入は破風窯の口広瀬戸茶入と本格の「わび」の道具揃え。客は懐石に「吸物」が出なかったので薄茶席に何かあると予期していたが、広間での薄茶席にもこれまた名物道具がうち揃い、客は「一々品評するは余りに煩雑」と言い出す始末。徹底して客をもてなすという濃厚な関西の茶風に、関東勢は辟易して退却する始末でした。 |