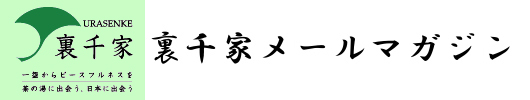 |
| 第82号(平成30年5月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『変わらぬこと』 伊住 公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:御香宮神社献茶式にて) |
|
こんにちは! 先月は、神社2カ所で御家元名代として献茶式をご奉仕させていただきました。 私が献茶式を名代として務めさせていただくようになって、もう5年は経つでしょうか。 会場まで参進する間、着座して台子と向き合う時、様々な場面で未だに緊張しております。 最初の頃はそれが手や足に伝わりブルブル、ガクガク。それこそ、点前どころではありませんでした。 でも近年は随分と落ち着いて臨めるようになりましたが。 そんな私には昔から変わらず続けている事があります。 それは、事前に点前をさせていただく場所、台子の位置等の写真を見るという事です。 何回も行った事がある場所でもです。 写真の情報量というものはたかがしれていますが、想像力を働かせ、気持ちを献茶式当日へむけていきます。 点前をしている自分の姿を想像し、会場の雰囲気を感じる。 ある意味私のルーチンワークかもしれません。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:益田非黙 ------------------------------------------------- |
| 先月ご紹介しました近代数寄者の代表的人物鈍翁・益田孝を、茶の湯の世界に引き込んだのは鈍翁の弟益田非黙(ひもく)でした。名は克徳(こくとく、または、かつのり)。庵号は無為庵(むいあん)。 非黙は慶応義塾を卒業後、司法省に入り官命によりイギリスに留学、法律制度を学びます。そして司法省を退任後、明治12年(1879)日本で最初の保険会社「東京海上保険」(現在の東京海上日動火災保険)を創業、その支配人となりました。 しかし、非黙は毎朝家を出ても会社の前を素通りして、茶道具商の店へ直行し、茶道具鑑賞に熱中するあまり、そのまま出勤しない日もあったようです。部下はそのような非黙に対し、専用の送迎係をおき、なんとか出社させようとしたそうです。 また非黙は非常に肥満していたため、正座が苦手で、胡坐(あぐら)で茶を飲んでいましたが、点前をする時は、茶色の木綿製の前垂れのような腰衣をつけて茶を点てました。このやり方は、同じように肥満していた兄の鈍翁も見倣ったそうです。 |