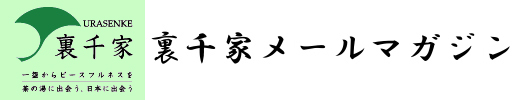 |
| 第80号(平成30年3月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『ななふくめ』 千 敬史 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:ナショナルコンファレンス2018 茶会にて) |
|
初釜が終わりホッとしたのも束の間、迫りくる多忙を春めく今日が予感させます。 こんにちは、千 敬史です。 さて、先日はナショナルコンファレンス2018が盛会裡に終了いたしました。私個人としましても鼎談、そしてオプショナルの薄茶席の亭主と、大変重みのある役割をいただき、難しくもやりがいのある3日間を過ごさせていただき感謝です。2年後の東京オリンピックイヤーは2020年、そして30路突入の私!と、何かとキリの良い(?)コンファレンス開催予定年になります。いよいよ同年代、そして年下も増えてくるであろう青年部。多くは語るまいですが、精進してまいりますので今後とも宜しくお願い申し上げます。 随分あたたかと言えど時おり冷える日もありますのでどうかご自愛ください。また各地で皆様とお会いするのを楽しみにしております。それでは! |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:井上世外 ------------------------------------------------- |
| 明治維新の混乱も収まり、日本が欧米各国のような近代国家への道を歩む中、茶の湯を担う新たな人達が政官財界から生まれます。「数寄者」(すきしゃ)と呼ばれた人達です。以後、昭和の初め頃まで彼らが茶の湯界をリードしました。今回から近代へと舞台は移ります。 近代の数寄者のトップに取り上げるのは、井上世外(せがい)です。世外って誰?と思われるでしょうが、不平等条約改正のため、「鹿鳴館」を舞台に、日本の欧化政策を進めた外務卿井上馨(かおる)のことです。ところで、以前より日本の演劇改良を考えていた世外は、明治20年4月、自宅(現在の東京・六本木の国際文化会館の地)で行った東大寺四聖坊の茶室八窓庵の移築披露茶会に明治天皇を招待して、その余興に歌舞伎を上演することにしました。この天覧歌舞伎の企ては成功し、天皇に認められた演劇として歌舞伎は息を吹き返すことになります。茶の湯が他の伝統文化興隆のために一役買ったのです。 一方、世外は茶道具収集にどん欲で強引なことで有名でした。招かれた茶会で気に入った道具があると、「もらっておく」と言って持ち帰ってしまったそうです。恐るべし世外の権勢。 |