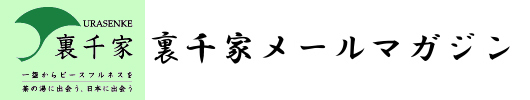 |
| 第79号(平成30年2月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『世相』 伊住 公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:大和学園茶室披きにて) |
|
こんにちは! 最強クラスの寒波が毎週のようにやってきており、毎日底冷えの日が続いております。 皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか。 宗家は1月いっぱいで初釜式含め各種初茶会も滞りなく終え、少し小休止といった感じです。 先日、子供にせがまれて大阪のUSJに行ってまいりました。 寒風吹き荒れる中、園内を走り回る子供を追いかけながら必死の思いで遊んでおりました。 冬休みという事で学生さんも沢山おりました。 そこで気が付いたのですが、最近の世相と申しますか、学生さんがまぁそこかしこでスマホ片手に写真を撮っているのです。 乗り物に乗るでもなく、楽しんでいる雰囲気でもなく。通行の邪魔になるような人もいました。写真を一通り撮り終えると、スマホをいじって会話もない。 何しにここへ来ているんだろうと少々冷めた目で見てしまいました。 インスタ映えという言葉が流行っております。いい写真を撮って褒めてもらいたい。 その向上心を別の方面に向けてもらいたいものです。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:伊木 三猿斎 ------------------------------------------------- |
| 伊木三猿斎(いぎさんえんさい)は、幕末・維新期の岡山藩の筆頭家老として藩政の舵取り役を務めた人物です。名は忠澄(ただすみ)。三猿斎は隠居してからの号ですが、こちらのほうでよく知られています。 玄々斎宗室に茶を学び、玄々斎から三猿斎に贈られた立礼棚一式が現存しています。この三猿斎、ある時「ひょうたん」で茶道具一式を作ろうとしました。4000個もの「ひょうたん」から選び、炭斗に始まり花入、煙管(きせる)、懐石の膳椀、皿、飯櫃、飯器などが作られました。茶碗はひょうたん形の伊賀焼、掛物はひょうたんの花入に椿を入れた画賛物でなんとか乗り切ったようです。何故、三猿斎は「ひょうたん」にこだわったのでしょうか、それは「ひょうたん」から作られた茶道具が、「わび茶」を象徴するものとされるからでしょう。伝来の利休居士や宗旦所持の炭斗、花入などを拝見すると、「わびた風情」が感じられます。 また三猿斎は、知行地の虫明(むしあげ、岡山県瀬戸内市)に虫明焼の窯を築き、京都から清風与平などの陶工を招き、多くの茶陶を作らせました。虫明焼は今も焼かれています。 |