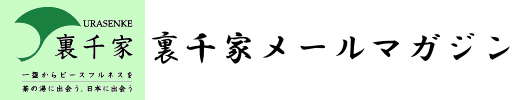 |
| 第75号(平成29年10月16日配信) |
| ------------------------------------------------- 『東京藝術大学130周年記念「藝大茶会」』 伊住禮次朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:藝大茶会(正木記念館)にて) |
|
こんにちは。伊住禮次朗です。光陰矢の如し、10月を迎えました。 当月は話題に事欠きませんが、今回は東京藝術大学130周年を記念して開催された「藝大茶会」の話をしようと思います。初めて席主をつとめさせていただいたのですが、家元席のほかには藝大席・美術倶楽部席が設けられておりました。藝大席では、大石膏室を舞台とした小沢剛氏の雲海の如き幻想的なインスタレーションの中で、裏千家茶道部の皆様におもてなしいただきました。使用された諸道具はすべて教授方のお手作り。一枚板のカウンターのような立礼卓の上には、優しい円みを帯びた雲を象った風炉/大学の徽章であるアカンサスの意匠を胴部に配したステンレス製の釜/巧みな金属加工が施された香合など、様々な道具が一列に配されており、心躍る創造的な空間でした。 私もいまだに学生をしながらお仕事をさせて頂いておりますが、今は博士論文執筆のラストスパート。とても良い刺激をいただき、気力を養うことができました。次にメルマガを書く時には、どんな報告ができているでしょうか…。不安は募りますが、あえてこの言葉で締めくくりたいと思います。乞うご期待! |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:田安慶頼 ------------------------------------------------- |
| 天保10年(1839)田安家当主・斉荘(なりたか)が尾張徳川家の第12代藩主となってしまい、当主不在となった田安家では、斉荘の義弟慶頼(よしより)がその跡を継ぎました。この慶頼も大変に茶の湯に熱心な人でした。 田安家には、裏千家11代玄々斎宗室の好みの茶室「富貴軒」(ふうきけん)が屋敷にありました。この茶室は、京都の数寄屋大工・初代木村清兵衛が造り、解体されて高瀬川から大坂を経て海路、江戸に送られ、隅田川をさかのぼって本所横網町にあった田安家下屋敷で組み立てられました。後に安田財閥の創始者安田善次郎(松翁)が入手しますが、関東大震災で焼失しています。 ある年の春、慶頼はこの「富貴軒」で時の大老井伊直弼を招いて茶会を催します。この茶会で用いられた花入は、太閤豊臣秀吉作の「大会」(だいえ)という根竹で作られた珍品中の珍品。竹の根っこが付いたままのもので、仙叟宗室の添え状が付いています。その添え状によれば、利休が所持していたというもので、現在は裏千家家元に所蔵されています。ここに裏千家と田安家の歴史的な縁が続いていることを想わせてくれます。 |