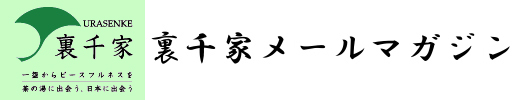 |
| 第74号(平成29年9月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『感謝』 千 万紀子 ------------------------------------------------- |
 |
| (初釜式お手伝いは永久不滅ですのでご安心ください!) |
|
京都は9月になった途端に秋めいてまいりました。よく日本は四季がはっきりしていると言われますが、それは単純に自然が豊かだとか寒暖差が大きいということだけではないと思います。日本人が“季節”を大切にし、例えば最近なら重陽の節句や十五夜など、日常の中で季節を感じられる工夫をしてきたからこそ、その移ろいがかたちとなって表れるのではないでしょうか。 宗家におりますと、毎朝利休御祖堂へ向かう茶室の設えからも今日がどのような日であるかを教えられます。家を出るまであと僅かとなり、今まで気にも留めなかったことに目が向き、当たり前と思っていた環境を大切にできるようになりました。結婚後もこの家で見たことや聞いたこと、感じたことを忘れずに過ごし、いつまでも裏千家の娘として恥ずかしくない生き方をしていきたいと思います。 皆様には右も左も分からない頃から温かくお見守りいただき有難うございました。決してお別れの挨拶ではありませんが、メールマガジンを書くのは最後になりますので、一言お礼を申し上げます。また、これからも敬史と伊住兄弟を宜しくお願い致します。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:徳川斉荘 ------------------------------------------------- |
| 徳川斉荘(とくがわなりたか)は、将軍家斉の第11子として江戸城で生まれました。4歳で「御三卿」(ごさんきょう)の一つ田安家の養子となり、26歳で田安家を継ぎますが、3年後の天保10年(1839)尾張徳川家の第12代藩主となりました。 この斉荘は茶の湯を好み、一行物や自作の香合、竹花入、茶碗など多くの好み道具を残していますが、「鯱香合」、「鯱鉾釜」などの名古屋城天守閣の屋根にあげられた「金の鯱鉾」(きんのしゃちほこ)に因んだものがあります。これは最初にお国入りした時に初めて見た名古屋城天守閣が、黄金に輝いていることに大変感動したためでした。 天保11年6月、斉荘は江戸戸山の下屋敷(戸山荘)で裏千家第11代玄々斎宗室から初歩の「小習十六ヶ条」から奥秘伝の「真台子」まで伝授されました。この戸山荘はほんの一部が「戸山公園」として残されていますが、もとは13万6千坪に及ぶ広大な面積をほこり、御殿や庭園のほかに東海道の小田原宿を再現した町並みが作られていました。伝授が終わり、京都に戻っていく玄々斎に「都辺の道みえぬまで白雪のふりかくしなばとまりもやせん」と、斉荘は別れを惜しむ和歌を贈っています。5か月にも及ぶ茶の湯伝授の間に、豊かな師弟関係が結ばれたことを想像させてくれます。 |