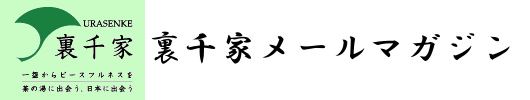 |
| 第73号(平成29年8月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『5ふくめ』 千 敬史 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:八坂神社献茶式にて) |
|
こんにちは! 忙しかった時期を経て、つかの間のリフレッシュな時期がやってまいりました。しっかりとここで心身共に充電し、また秋から東奔西走、頑張っていきたいと思います。 写真は八坂神社さんでのお献茶式のものです。午前中とはいえ暑いものは暑く、着物なのでなおさらではありましたが、お茶席にも大勢の方にお運びをいただけまして、無事滞りなく1日を終えることができました(私はただ居ただけですが)。体感では私が小さかった頃の方が暑かった気がするのですが、実際は年々少しずつ気温が上がってきているようですね。 上手に太陽とお付き合いして、いっしょに夏を乗り切りましょう。 それではまた9月より元気に各地でお会いしましょう。良い夏をお過ごしください! 千 敬史でした。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:青木宗鳳 ------------------------------------------------- |
| 青木宗鳳(あおきそうほう)は、享保年間(1716〜36)から宝暦年間(1751〜64)にかけて、大坂で遠州流の茶人として活躍しました。 後に宗鳳は師匠から独立し、独自の遠州流を打ち立て家元となります。その過程において宗鳳は膨大な茶書を集め、また自らの著作も加え、その数は88部149冊にのぼりました。なかでもこの連載で取りあげた松屋と松花堂の名物拝見記録を書き残しています。松屋では「鷺の絵」と「松屋肩衝」・「存星盆」の三名物を、松花堂では「国司茄子」をはじめとする松花堂名物をそれぞれ拝見しています。しかし、松屋が昔の勢いを無くし、「茶入を以、今ニ而ハ一身を立てられ候」と、名物道具の拝見で収入を得ていたことを暴露し、また松花堂では、待合で「滝本好み、四角にして薄く、折敷程有而、中を十文字に仕切を入」と後の「松花堂弁当」の容器となったものの原型であろう煙草盆に注目するなど、貴重な記録となっています。 |