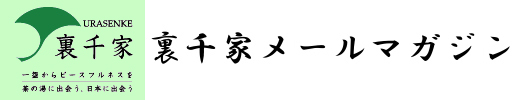 |
| 第72号(平成29年7月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『京都の熱い夏』 伊住 公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:昨年の祇園祭にて・裏千家担当「八幡山」) |
|
こんにちは! 今月はいよいよ祇園祭が催行されます。 私は昨年より祇園祭のボランティア団体に参加しており、ただいま準備で大忙しです! 今年は八坂神社献茶式も裏千家がご奉仕の番。 無病息災を祈念する、京都をあげての神事です。 献茶式、山鉾巡行ともに滞りなくすみますように。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:鴻池道億 ------------------------------------------------- |
| 鴻池道億(こうのいけどうおく)は大坂の豪商として知られる鴻池家の一族でした。鴻池家は酒造業に従事し、それまでの濁り酒から清酒を造り出して、さらには海運業・両替商など幅広く手掛けますが、後には両替商に一本化し、大坂の「十人両替」の一家として莫大な富を築きあげ、三井家や広岡家と並び称される豪商となりました。 ところで、茶の湯にとって第一に必要なものとして「目利き」を利休の高弟山上宗二は挙げています。この目利きとは本来「わび茶にかなう」道具であるかどうかを判別する能力を指していたのですが、江戸時代になると目利きは道具の真偽と来由を知っている人という意味に変わります。このような江戸時代的な意味での目利きとして知られたのが道億でした。鴻池一族はその財力を基として多くの茶道具を集めていましたから、道億も様々な茶道具を目の当りにして、茶道具の鑑定に優れていました。ある時、博学で知られる予楽院近衛家凞(よらくいんこのえいえひろ)に、侍医の山科道安が中興名物(ちゅうこうめいぶつ)の「西施茶入(せいしちゃいれ)」を見せたところ予楽院は知らなかったらしく、道億にこの茶入について尋ねさせますと、たちどころに詳しい伝来や特徴を述べたそうです。 |