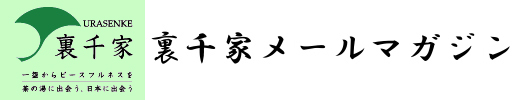 |
| 第70号(平成29年5月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『ご報告』 千 万紀子 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:裏千家学園茶道専門学校の壮行会にて卒業生よりお祝いをしていただいて) |
|
すでにご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、この秋に結婚することになりました。総会で発表しましてからたくさんの温かいお言葉を頂戴し、大変嬉しく思っております。 結婚後も宗家内での行事などはお手伝いさせていただくつもりをしていますが、今のように全国を飛び回ることはございません。大学病院に勤める彼は非常に忙しく、転勤や留学も有り得るそうです。彼の生活に合わせ、いつも万全な状態で患者さんに向き合えるようサポートしていくのが私の新たな役目となります。 せっかくここまでお仕事をしてきたのに勿体無いと言っていただくこともあります。たしかに茶道は私が持って生まれたツールです。だからこそ、このツールは結婚したからといって失うものではなく、ひとまずしまっておいても必要になったときにはすぐに取り出すことができるのです。 入庵して7年とはいえ、裏千家の中心で29年間過ごしてまいりました。ここで少し外から客観的に我が家を見ることで、自分がこの先やるべきことに気付くのではないかと思います。 夏まではお家元の随行をさせていただきますが、単独でのお仕事は少しずつ終わりを迎えています。4月には中宮寺さまで最後の献茶式をご奉仕させていただき、今月末の山梨青年部50周年が淡交会行事の締めくくりとなります。 あと数ヶ月、各地で皆様との楽しい思い出を一つでも多く作れますように! P.S. 冒頭の写真は父が撮ってくれたものです。ブレているのは涙で手が震えたのか、はたまた酔っ払っていたのか… |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:酒井宗雅 ------------------------------------------------- |
| 松平不昧(ふまい)の弟子、酒井宗雅(さかいそうが)は播磨国(兵庫県)姫路藩主で、名乗りは忠以(ただざね)、弟に江戸後期を代表する琳派(りんぱ)の画家酒井抱一(ほういつ)がいます。 宗雅は不昧に茶の湯を学びましたが、二人とも参勤交代により江戸と領地を行き来しなければならぬ大名でしたので、直接教えを受ける以外に、手紙のやり取りによる「通信教育」によって指南を受けることも多々ありました。 宗雅は、師の不昧同様、茶道具に深い関心を持っていましたが、江戸時代初期の茶人、八幡滝本坊の社僧だった松花堂昭乗(しょうかどうしょうじょう)が所蔵した名物茶道具「八幡名物」(やわためいぶつ)が同坊から流出したのを惜しみ、天明5年(1785)ころから収集し、入手した「八幡名物」24点を、同8年12月に滝本坊へ寄贈したことはよく知られています。 幸いにも、謝礼として宗雅へ贈られた3点の茶道具のうち、「備前半月水指」が現存しており、その優美な姿はいかにも宗雅への贈物としてふさわしいものです。 |