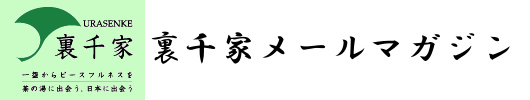 |
| 第68号(平成29年3月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『開き直り』 伊住 公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:久留米支部創立65周年・青年部50周年記念行事にて) |
|
こんにちは! 少し春らしい気候になったかと思えば、また寒くなったりと、いつまでたってもコートを仕舞うことができない日々が続いております。 先月末の事ですが、久留米支部・青年部の周年行事にお伺いしました。 私が宗家を代表して出席したわけですが、単独出張には私にとって最大の障壁があります。 それは式典での挨拶と講演です。 私、人前で話すのが非常に苦手なんです。まぁ好きな人は珍しいと思いますが。 いつも緊張から手に汗びっしょり、足がプルプル。 でも、前回初めて三重で講演をした時もそうだったのですが、直前になると変に開き直るんです。人間って不思議なものです。 今回の久留米も皆さんに熱心に聞いていただいたおかげで、与えられた時間、しっかり話しきる事ができた次第です。 こんな私ですが、温かい目で今後ともお見守りください。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:近衛予楽院 ------------------------------------------------- |
| 近衛予楽院(このえよらくいん)は、江戸時代中頃の公家で、名は家熈(いえひろ)、院号を予楽院といいました。近衛家は、御堂関白藤原道長の流れをくむ、公家の中でも最高の家格にあり、歴代から関白・摂政を輩出しています。家熈も宝永4年(1707)関白に、同6年には中御門(なかみかど)天皇の摂政に就任しています。茶の湯は常修院宮慈胤法親王(じょうしゅういんのみや じいんほっしんのう)などから学びました。 ある時、公家で茶人でもあった風早実種(かざはや さねたね)が奈良で買い求めた大きな瓢箪を予楽院のもとに持ち込んで、花入にしてくれるよう頼みこんできました。すると予楽院は瓢箪の上下を切り取って花入にし、「大和歌」(やまとうた)という銘をつけて実種に戻しました。瓢箪は旧仮名遣いでは「へうたん」と読みましたので、その上下を切ると「うた=歌」が残るという言葉遊びです。同様に奈良=大和で買い求めたということで、このような銘にしたようですが、なんと優雅なことでしょう。 |