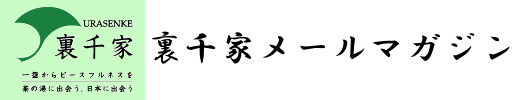 |
| 第67号(平成29年2月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『そうだ、今日、やろう』 伊住禮次朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:茶道資料館呈茶席 映像コーナーにて) |
|
こんにちは、伊住禮次朗です。本年もよろしくお願い申し上げます。 私事ですが、数年前まで少しだけ地唄三味線のお稽古をしていました。大阪への通勤など様々な事情が重なったことで、しばらく休止状態だったのですが、最近はどうにか再開したいという想いを強くしています。 しかし、再開するにもパワーが必要なものですね。特に、ご無沙汰してしまった先生のことを考えると二の足を踏んでしまいます。稽古事に限らず、どのようなことでも長く続けるのは大変なことで、「継続は力なり」とは申しますが、「継続には力が必要」というのも真理だと思います。様々な努力の継続が、結果的に自身の強みになるのでしょう。 我が身を振り返れば、最近はジム通いもさぼり気味…。本年の稽古始めに掛けられた元伯宗旦居士「万里一條鉄」の意を噛みしめて、何事につけても「明日やろう」という考えがちらつく自分をできる限り戒めたいと思っております。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:後西天皇 ------------------------------------------------- |
| 後西(ごさい)天皇は、後水尾天皇の皇子で、高松宮家を継承していましたが、兄の後光明(ごこうみょう)天皇の急逝により、明暦2年(1656)に第111代の天皇となります。若い時から茶の湯に関心をもち、自作の竹花入や茶杓などが残されています。寛文3年(1663)には弟の霊元(れいげん)天皇に譲位して上皇となりました。 譲位後はさらに茶の湯に力をそそぎ、自らの御所の御殿内や庭に茶室を造りました。庭の池の中島には「環波亭(かんぱてい)」、築山の頂きには「畳嶂台(じょうしようだい)」という茶室があり、それらを使いたびたび茶会を催しました。 延宝7年(1679)7月2日の茶会には、叔父で茶の湯の師である常修院宮(三千院門跡)慈胤法親王(じょうしゅういんのみや じいんほっしんのう)などを招きました。中立の後、自ら濃茶を練りましたが、客より先に自分が飲み、次に客へという有りさま。茶席における主・客の関係や師弟関係、叔父・甥という血縁関係も意に介さない、いかにも元天皇らしい振る舞いといえましょう。 |