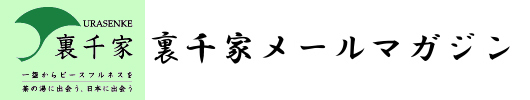 |
| 第66号(平成29年1月16日配信) |
| ------------------------------------------------- 『丁酉年』 千 万紀子 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:稽古始めにて) |
|
穏やかな新年をお迎えになったことと思います。酉年生まれは十二支の中で最も人数が少ないそうですが、当たり年の方いらっしゃるでしょうか。向かい干支は正反対の性質を持つため互いに足りないものを補い合える、相性が良いとされており、卯年の私にとっては酉年になります。感謝してもしきれない恩師も、公私ともに頼りにしている親戚も、モチベーションと言える大切な人も、私を導いてくれる存在は酉年ばかりなので納得させられます。年齢を重ねるごとに日本古来の考えに魅力を感じ、それが正しいかどうかではなく発想の豊かさを誇らしく思うのです。 本年が皆さまにトリまして飛躍の年になりますように! |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:松平定信 ------------------------------------------------- |
| 江戸時代後半、「寛政の改革」(かんせいのかいかく)が行われました。この幕政改革を主導したのが、奥州の白河(福島県)藩主の松平定信(まつだいらさだのぶ)でした。「天明の飢饉」(てんめいのききん)のさなかに家督を継いだ定信は、農村対策に成功し、一人の餓死者も白河藩内からは出さなかったという藩政の実績が評価され、老中首座に抜擢されます。前代の田沼意次(たぬまおきつぐ)の賄賂政治を批判し、改革に乗り出しますが、庶民の着物の柄まで制限するという厳格な倹約令などが反感を買い、「白河の清きに魚も住みかねてもとの濁りの田沼恋しき」と狂歌にも詠まれるほど不人気で、6年ほどで老中を解任されてしまいました。 定信は『茶道訓』(ちゃどうくん)などの茶書を著わした茶人であり、「士庶共楽」(ししょきょうらく=武士も庶民も共に楽しむ)という理念を掲げて、白河に日本最古の公園「南湖」(なんこ)を造り、そこに「共楽亭」という茶室を建て、その理念を実現しようとしました。華美を嫌い、質素な茶を好んだ定信は、『茶道訓』の中で道徳を守るところに茶の本意があると述べています。 |