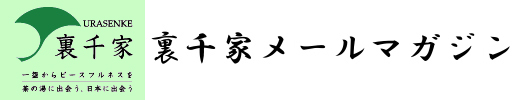 |
| 第64号(平成28年11月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『継続』 伊住 公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:洛趣会にて) |
|
こんにちは!気づけばもう11月。そして、ようやく私の番が回ってまいりました。 大体この時期は同じ話をしておりますが、今年も洛趣会に席主として参加させていただきました。 もう80年以上続いている会ですが、私もお手伝いをさせていただくようになって5年目を迎えます。 なにもわからない時期から席主をさせていただき、しどろもどろだった道具の説明なども、少しはマシになり(?)本当に洛趣会に育てていただいた感じがします。 長くご縁を頂戴できている事に、また自分の与えられたフィールドがある心地よさに感謝です。 相変わりませず。会員の方とも顔なじみが増えて、よりリラックスして臨めているのも『継続は力なり』まさにその言葉に尽きます。 身一つで飛び込んでみた先に道があった。今後も任せていただける限り、自分の責任を継続していければと思います。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:久須美疎安 ------------------------------------------------- |
| 久須美疎安(くすみそあん)は、京都の上京(かみぎょう)に生まれ、生家は、漆器を扱う中嶋屋という商家でした。名は小兵衛。洗竹庵(せんちくあん)と号しました。茶の湯は義父の藤村庸軒から学んだようですが、千宗旦最晩年の弟子とも言われます。京都で「町屋の倒壊1000余軒」といわれた寛文2年(1662)5月の「寛文京都地震」の後、上京から鴨川を渡った岡崎(現京都市左京区)の地へ移り、「河東散人」(かとうさんじん)とも号しました。 疎安は、義父庸軒が千 宗旦から聞いていた様々な話を書き留めていたものを、『茶話指月集』(ちゃわしげつしゅう)として元禄14年(1701)に出版しました。茶の湯逸話集として最初に公刊されたものです。茶会での話題は俗事(政治や訴訟の話など)は禁じられていましたから、茶の湯話、なかでも茶人の逸話がふさわしいものでした。有名な利休の朝顔の茶会では、「その後、遠州公のころより、露地に花を植えられず」とあり、露地に花の咲く木が植えられなくなった時期が疎安によって明らかにされています。 |
| ------------------------------------------------- 今日庵通信:兜門改修工事 ------------------------------------------------- |
 |
| 平成25年から着手されている今日庵全域の茶室解体修復工事の一環として、本年8月より裏千家今日庵のシンボルともいえる「兜門」の修復が始まっておりましたが、今月装いも新たにお目見えしました。 |