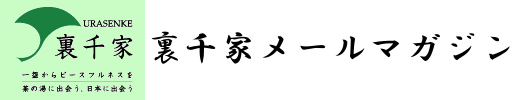 |
| 第63号(平成28年10月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『看脚下』 伊住 禮次朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:茶道資料館にて) |
|
こんにちは。伊住禮次朗です。10月を迎えて朝晩涼しくなってまいりました。台風一過、肌に感じる風も清らかな心地がします。 朝方に茶道会館の前を歩いていた折、なんとなく秋の雰囲気を探して空を見上げていたのですが、感じたのは刺激臭。足元に置かれたバケツには銀杏の実がぎっしりと詰まっており、居合わせた人と「時期ですね〜」と言いながら、本格的な秋の訪れを感じたひと時でした。暦ではとうに秋だといわれると、確かにそうなのですが…。 さて、茶道資料館で「秋」といえば特別展!現在は、秋季特別展「私の一碗−六十五碗 それぞれの想い−」が開催中です(12月11日まで)。京都を中心とした美術館や老舗企業の代表者の方々、知名士の皆さまなどからお心入れの一碗をご出品いただいており、学芸員が作品を選定する企画展とは一味違った展覧会だと思います。美術の秋というと押し付けがましい気もいたしますが、お出かけするには気持ちのいい季節。皆さまのご来館をお待ちしております。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:壁塗土斎 ------------------------------------------------- |
| 千 宗旦の深い影響をうけて茶道に志した一人として、壁塗土斎(かべぬりどさい)がいました。壁塗り、今でいう左官(さかん)を職業とする人物で、姓は岸本、名を市助といいました。土斎の号は宗旦から贈られたともいわれています。 ある時、宗旦に呼ばれて壁塗りの仕事を進める間、そばで宗旦が黙々と茶を点てていました。その姿に大変感動した土斎は、宗旦に弟子入りを願い出ます。宗旦はこの願いを心よく許しましたので、土斎は家に戻るとすぐさま頭を丸め、十徳(じっとく)を羽織った茶人のかっこうで稽古にやってきたそうです。これは宗旦のスタイルをそっくりとまねたものでした。宗旦が半ばあきれながらその理由を聞くと、「お弟子にしていただいた上は、せめて姿かたちだけでも師匠に似せたかった」とのことでした。やがて土斎は、宗旦が出かける茶会のお伴を最もよくつとめる弟子となりました。 ところで、土斎の塗る床には特徴がありました。床の内の、普通は板張や畳にする部分にも壁土を塗り、上から紙を張るというもので、「土斎床(どさいどこ)」とも「土床(つちどこ)」ともよばれ、宗旦の好みと伝えられています。 |