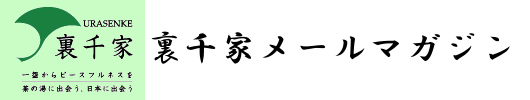 |
| 第61号(平成28年8月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『にふくめ』 千 敬史 ------------------------------------------------- |
 |
| 写真:アクアマリンふくしまにて) ナショナルコンファレンス2016 inいわき のコース別研修 No10「アクアマリンふくしま」の見学〜水族館が震災から学んだこと〜 に参加中の1コマ |
|
遡ること2ヶ月。いわきの地に497名の若き青年茶人の方々(若くない方もいますが・・・)が集い、ナショナルコンファレンスが開催されました。被災の現実を知るためのコース別研修、そして趣向を凝らしたお茶席で精いっぱい頑張る皆さんの姿が、若い私がさらに若くなる程のエネルギーを与えてくれました。この熱い気持ちを忘れず、暑い夏を、人情に篤く過ごしていきたいと思います。面の皮は厚くならないように・・・。 あらためましてこんにちは。本当に暑いので皆さん体には十分気を付けてくださいね。そして良いお盆をお過ごしください。千 敬史がお送りいたしました。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:北村幽庵 ------------------------------------------------- |
| 茶の湯者に必要な要素として作意とか目利きなどがありますが、味覚もその一つと言えるかもしれません。この味覚に優れた人に北村幽庵(きたむらゆうあん)がいました。幽庵焼という料理法を考案したことが知られます。 幽庵は、近江の堅田(滋賀県大津市)の郷士の家に生まれたので、堅田の幽庵とも呼ばれました。茶の湯の師は前号に登場した藤村庸軒です。幽庵がいた堅田は、琵琶湖の水運の拠点として中世以来栄えた所でした。 幽庵は茶会に琵琶湖の水を使っていましたが、ある時、湖の中心の水を汲んでくるよう下僕に命じました。汲んできた水を一口飲んだ幽庵は、これは湖の中心の水ではないと断定します。そして半分ほど水を流させてもう一度飲んだところ、ここからが中心の水だと、言いました。実は、水を汲んで帰る途中、船が大きく揺れ、半分ほどこぼれてしまい、しかたなく下僕が岸近くの水を継ぎ足してきたのでした。『茶経』の著者陸羽にも似たような話がありますが、味覚に優れた幽庵らしい話といえましょう。 |