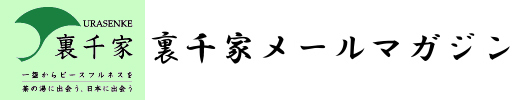 |
| 第53号(平成27年12月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『歴史』 伊住公一朗 ------------------------------------------------- |
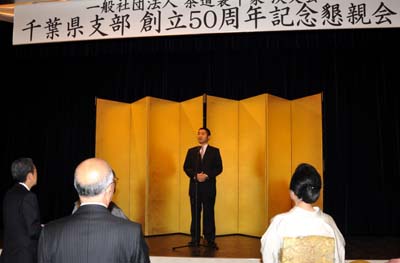 |
| (写真:千葉県支部創立50周年記念大会にて) |
|
こんにちは! 今年も残すところあとわずか。 先月末に千葉県支部の周年行事、献茶式にお家元の随行でまいりました。 年内最後の出張、また献茶式ということでホッとしながら家路につきました。 今年も沢山の出会いがあり、また別れもあり。 カレンダーで見ると一年というのはあっさりしていますが、実際は一日、一日にストーリーがあります。 仕事が上手くいった日。気分の落ち込んでいた日。嬉しかった日。 一日が一年になり、積もり積もって過去になり、歴史になります。 2016年は皆さんもどんな『歴史』を刻まれるでしょうか。 今年もメルマガにお付き合いいただきありがとうございました。 来年も相変わりませず宜しくお願いいたします。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:本阿弥光悦 ------------------------------------------------- |
| 今年は「琳派400年」の年として多くの催しが開かれました。「琳派(りんぱ)」とは、江戸時代の画家、尾形光琳の「琳」をとって名付けられた絵画の流派をいいます。光琳は、「燕子花図屏風(かきつばたずびょうぶ)」や、「紅白梅図屏風」などの作品でよく知られていますが、この「琳派」の祖といわれる本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)が、京都・鷹峯(たかがみね)の土地を徳川家康から拝領して、ちょうど400年たったことにより記念の年とされたものです。 光悦の本阿弥家は、刀剣の研ぎ、鑑定などをする家として足利将軍家から代々重んじられました。光悦は家業に従事する一方、書や漆芸において重要な作品を遺すなど、江戸時代初期の第一級の文化人でした。 作陶においても、楽家二代の常慶(じょうけい)に手ほどきを受け、幾つかの名碗を遺していますが、その最高峰とされるものは、長野県のサンリツ服部美術館に所蔵される国宝・白楽茶碗「不二山」です。一見して富士山を連想させるその姿は、多くの人を魅了してきました。茶碗を納める箱には「不二山 太虚庵(たいきょあん)」と作者の光悦自身が銘と自らの号を書いており、初めての共箱(ともばこ)としても知られています。なぜ光悦がこのようなことを試みたかは、この茶碗が愛娘の嫁入り支度の代わりだったという伝承を考えると、光悦が本作品に込めた思いの深さによるものと言えるでしょう。 |