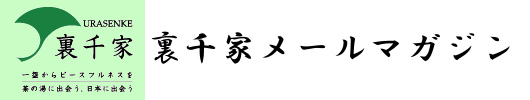 |
| 第52号(平成27年11月16日配信) |
| ------------------------------------------------- 『単独』 伊住公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:洛趣会にて) |
|
こんにちは! 前回のメルマガ配信から今日までにかけて、単独の出張・行事が盛り沢山の1ヶ月でした。 黒住教献茶式にはじまり、多賀大社献茶式、生国魂神社献茶式、UIA30周年行事、洛趣会。 気づけばもう11月半ばです。 最近は宗家の若手だけで出張するケースも随分増えてきました。 「はじめてのおつかい」ではないですが、1つの仕事を任されるというのは本当に嬉しく、勉強にもなります。 まだまだ頼りない若手年長者ではありますが、少しでも戦力になれればと日々奮闘しております。皆さんも誰かに頼りにされると張り切りませんか? |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:烏丸光広 ------------------------------------------------- |
| 江戸時代の初め、寛永年間(1624〜44)の京都では多くの文化人が出て、それぞれ文化サロンを形成しました。なかでも後水尾(ごみずのお)天皇を中心とした公家の文化サロンは格別な存在でした。このサロンの中心的メンバーの一人が公家の烏丸光広(からすまるみつひろ)です。烏丸家は和歌の家なので、光広が和歌を得意としたことは当然ですが、能書家でもあり、茶の湯もよくたしなみました。 その光広と、京都誓願寺の住職安楽庵策伝(あんらくあんさくでん)、大坂の豪商淀屋个庵(こあん)が、仙洞御所(せんとうごしょ)で詠んだ連句がのこされています。 冬の夜や、ゆるりゆるりとまはり炭 (光広) さむさ(寒)もしらでをき(置き)あかす袖 (策伝) 衾(ふすま)をも夜衣もしちや(質屋)に持行て (个庵) 光広の発句に、炉に炭をつぐ「廻り炭」(まわりずみ)が読み込まれている点は、注目されることです。このことは、光広の日頃の茶の湯のたしなみの程を推測させるものと言えるからです。 |