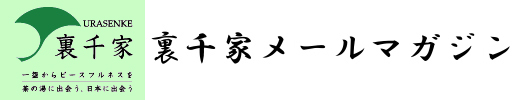 |
| 第50号(平成27年9月15日配信) |
| 東日本豪雨により水害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 |
| ------------------------------------------------- 『地域の色』 伊住公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:金沢今日会にて) |
|
こんにちは! 随分暑い日の多かった7月・8月を越え、ようやく過ごしやすい気候となりました。 9月に入りますと、出張で各地に赴く機会が増えてまいります。 その際の楽しみが、支部の皆様の懸釜にお邪魔し一服頂戴すること。 地方ごとに特色のあるお菓子。 地元で活躍される作家さんの道具。 時季や地方によって様々な花。 席主さん心入れの「見立て」や「あそび」。 伺った場所ならではの趣向を凝らした茶席が何よりのご馳走で、とても勉強になります。 今月はどんな驚きや出会いがあるか、今から楽しみです。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:本願寺教如(きょうにょ) ------------------------------------------------- |
| 戦国時代、加賀一向一揆(かがいっこういっき)により加賀国(石川県南部)を支配し、また本拠地大坂からの退去を要求してきた織田信長に対して、全国の門徒や戦国大名を巻き込み10年もの間徹底抗戦し続けた本願寺は、江戸時代の初め、慶長年間(1596〜1611年)に東西に分立しました。 11代門主(もんしゅ)顕如(けんにょ)の没後、嫡男の教如が本願寺を継ぎますが、豊臣秀吉は父の大坂退去後も信長に抗戦し続けたことを主な理由として、教如をすぐに隠退させ、弟の准如(じゅんにょ)を門主にします。教如は、関ヶ原の合戦ののち、徳川家康から現在の東本願寺の土地の寄進を受け、自らの本願寺を打ち立てたのでした。 教如は茶の湯を大変好み、これを介しての交友関係も豊富で、千利休や、織田有楽、前田利長、金森長近、細川忠興、蒲生氏郷などの戦国武将との関係が知られます。なかでも、信長の弟、織田有楽(うらく)と飛騨高山藩主の金森長近(ながちか)とは、特に親しかったようです。 近年発見された金森長近宛の教如の手紙に、「京都にお出でになるとのことですが、(京都にお住いの)有楽様と誘い合わせて遊びにいらしてください。久し振りに、茶を飲みながら一日中茶の湯の話をしましょう。必ずお出でくださいよ。」と書かれていました。教如にとって茶の湯とは、本願寺の外交手段であった一方、気を許しあった茶友との楽しい語らいの場を与えてくれるものであったことが、この手紙からも分かります。 |