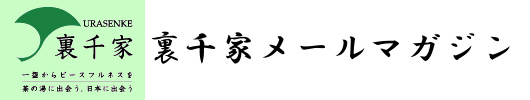 |
| 第49号(平成27年8月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『解釈』 伊住公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:八坂神社献茶式にて) |
|
こんにちは! 世間では夏休み真っ只中。皆さん思い思いの休みを楽しまれていることでしょう。 私も少しばかり休暇をいただき、長男と戯れながら高校野球をテレビ観戦して英気を養いました。 話は変わりますが、最近非常に面白いなと思うのが、掛け軸に対する解釈の仕方です。 先日、知人が軸に何と書いてあるかわからず困っているとのことで、拝見しました。確かに、独特な崩し方の筆致でなかなか骨の折れる軸でした。私もいろいろと禅語辞典、くずし字辞典とにらめっこしながら自分なりの解釈をお伝えしました。 その方が「なるほど!そういう見方もありますね。ちなみに私はこう思うのですが・・・」と、そこから談義に花が咲きました。 それでいいのだと思います。勿論、本質的な部分で正解はあるのでしょうが、それぞれの立場や状況で柔軟に解釈する──それが茶の湯の楽しみでもあるのだなぁと、しみじみ思った次第です。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:伊達政宗 ------------------------------------------------- |
| 独眼竜政宗こと、伊達政宗は戦国時代、出羽国米沢城(山形県米沢市)で伊達輝宗の嫡男として生まれました。幼少時に天然痘にかかり、右目を失います。天正12年(1584)家督を相続し、17代目当主となってからは積極的に勢力拡大を図り、天正17年には磐梯山麓(ばんだいさんろく)摺上原(すりあげはら)の戦いで、会津の蘆名義広(あしなよしひろ)を破って南奥州の覇権を確立しました。 摺上原の戦いの翌年、北条氏の根拠地小田原城は豊臣方に包囲されます。父の代から同盟関係にあった北条氏を見限ることを迷った政宗は、容易に秀吉のもとに参陣しませんでしたが、その命運が尽きようとするのを見て、ようやく秀吉に面会に行きます。上洛命令を無視し、小田原にも遅く参陣した政宗に怒った秀吉は、面会を許さず、箱根の底倉(そこくら)の地で謹慎するよう命じます。そこは、現在の箱根登山鉄道の「宮ノ下駅」と「小涌谷駅」の間にある、早川の支流蛇骨川(じゃこつがわ)が流れる深い谷でした。 後日、政宗は秀吉の命に従わず会津を攻め取り、さらに遅参した理由を詰問にきた使者の前田利家たちに対し、命乞いをするどころか、「この度は利休殿も参陣していると聞いておりますが、もしそうならば、政宗が是非茶の湯の話を聞かせて欲しいと申していると、使者の方々よりお伝え下さい」と使者たちに懇願しました。これを聞いた秀吉は、「自らの命が危ない時に、利休から茶の湯の話を聞きたいなどという者がいるとは。どうやら政宗はわしに逆らう気持ちはないようだ」と言って、切腹を免じ、二日後には政宗と面会したということです。茶の湯には思わぬ力があるようです。 |