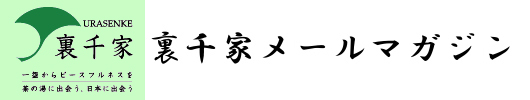 |
| 第48号(平成27年7月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『代を重ねる』 伊住公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:貴船神社献茶式にて) |
|
こんにちは! 梅雨真っ只中、連日湿気がすごくムシムシしますね。 さて私事ですが、先日第一子の長男が誕生しました。 母子ともに健康で、無事に産まれてくれた事に本当に感謝しかありません。 私もついに父親となりました。不思議な感覚です。 私は父を高校生の頃に亡くしました。 父は家族の前では仕事の話を一切しない人でした。 忙しい人でしたがよく遊んでくれました。よく正座をさせられ弟と怒られました。 背中で語っていたのでしょうか。 気づけば私も父と同じ道を歩んでいます。 産まれてきた息子はどんな道を歩んでくれるのか。今から楽しみです。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:島津義弘 ------------------------------------------------- |
| 島津氏は鎌倉時代のはじめ、九州の薩摩・大隅(おおすみ)二か国(鹿児島県)と日向(宮崎県)の守護(しゅご)に任ぜられて以来、南九州で勢力を強めました。戦国時代になると、島津貴久(たかひさ)は薩摩・大隅を統合、その子義久はほぼ九州を制圧する勢いでしたが、豊臣秀吉の「九州平定」によりその野望は断たれ、薩摩・大隅と日向の一部の領主になりました。 義久の弟の一人が島津義弘で、武勇の誉れ高く、無類の戦上手(いくさじょうず)として知られ、兄に代わり島津軍の総大将を務めたこともありました。「文禄の役」では戦功により、秀吉から恩賞として、大名物(おおめいぶつ)「平野肩衝」(ひらのかたつき)を授かっています。後に維新斎(いしんさい)と号したため、「維新公」と敬称されました。 義弘は武勇に秀でたばかりでなく、戦場医術にも詳しく、茶の湯にはとりわけ熱心だったようです。鹿児島県立図書館には、義弘が千利休に茶の湯について質問した『維新様より利休え御尋之條書』という写本が所蔵されています。本書は琉球の王族、護得久家(ごえくけ)に伝わったというもので、49ヶ条の問答により構成され、その1ヶ条目は、「茶会の時、亭主は客をどこでお迎えしたら良いのですか」という具体的なもので、この質問に対し利休は、「その場所はお客様により、茶室から遠い所、近い所という違いがあります。お見送りする時も同じですよ」と答えています。 義弘にとって茶の湯は情報交換の場でもあったでしょうが、戦塵にまみれた自身の心の渇きを潤す場でもあったようで、武将のたしなみにふさわしいものと考えていたようです。 |