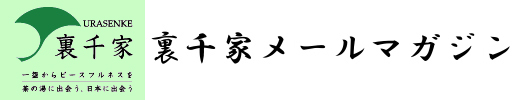 |
| 第47号(平成27年6月16日配信) |
| ------------------------------------------------- 『後輩たち』 伊住公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:鎌倉大仏献茶式にて) |
|
こんにちは! 全国的に梅雨入りし、はっきりしない天気が続きますね。 私は先日、母校である立命館大学の茶道研究部春季茶会にお邪魔してきました。 在学中は私も茶道研究部に所属し、同期と稽古に励んだものです。 卒業して初めて後輩の茶会へ参加したのですが、私が学生だった頃よりも随分とレベルアップした頼もしい姿に驚きました。 昔は指導者がおらず、学生同士で教えあっていたのが近年は学外から指導者を招き、稽古も内容が濃くなり、皆の動きが格段に良くなっていました。 裏研(裏千家学生茶道研究会)にも積極的に参加しており、ライバル同志社にも負けない素晴らしい部となりOBとしては安心しました。 着物もしっかりと着こなし、テキパキと動く後輩たち。 少しジェラシーを感じつつ、時の流れを感じた次第です。 梅雨の鬱陶しさを忘れさせてくれる、そんな爽やかな茶会でした。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:上田宗箇(そうこ) ------------------------------------------------- |
| 関ヶ原の戦いにより政権の主は豊臣氏から、徳川氏へと移り、大坂冬の陣・夏の陣により豊臣氏は歴史の舞台から姿を消します。織田・豊臣・徳川の時代を生きた武将に上田重安(しげやす)がいます。重安は宗箇ともいい、後に広島に自らの茶の湯を遺しました。宗箇は、はじめ織田家の家臣丹羽氏に仕え、ついで豊臣秀吉から越前国(福井県)に1万石を与えられます。茶の湯は千利休に学び、利休没後は古田織部と親交を結びました。関ヶ原の合戦で西軍に属したため、領地を失いますが、和歌山の浅野家に1万石で召し抱えられました。同家が広島に転封した際に、1万7千石に加増されています。 慶長20年(1620)4月、大坂夏の陣において、宗箇は主人の浅野長晟(ながあきら)に従い、和歌山城を出陣。和泉国(大阪府)の樫井(かしわい)で大坂方の猛将塙団右衛門(ばんだんうえもん)らと激突しました。しかし大坂方の勢いに押され、味方は総崩れとなります。その際、宗箇は追撃してくる団右衛門らを待ち受けながら手近にあった竹を手に取り、ゆうゆうと削ったのが、「敵がくれ」と銘をつけられた2本の茶杓で、今に残されています。この茶杓は通常の宗箇のものとは違い、櫂先がゆるやかで平らであるなど、いかにも戦場で削られたということを感じさせてくれます。非常時でも茶の湯に心を向けることができた宗箇の大胆不敵さには驚かされます。 |