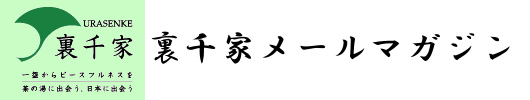 |
| 第46号(平成27年5月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『流鏑馬神事』 伊住公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:下鴨神社にて) |
|
こんにちは! 5月に入り天気の良い日が続きましたね。皆さんはGW、如何お過ごしでしたか? 私は3日に下鴨神社で行われた流鏑馬神事(やぶさめしんじ)に参加してきました。 神事の中心となる「長官代」というお役をいただき、滞りなくお務めを終えることができました。このお役は大宗匠、また亡き父も務めたもので、三代にわたる長官代は初だそうです。 大変感慨深く、良い経験をさせていただきました。 この流鏑馬神事は葵祭の前祭にあたり、本日15日が葵祭当日。京都は賑わいを見せております。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:丿観(へちかん) ------------------------------------------------- |
| 丿観の生没年ははっきりしませんが、京都の山科という所に住み、利休や秀吉と同じ時代を過ごした人のようです。釜は「手取り釜」1つしか持たず、それで食事をし、済めば谷川の清流で釜を洗って炉に懸け、茶の湯を行っていたという「わび数寄」の茶人でした。 この丿観が利休を茶会に招いたことがありました。利休が約束の日時に丿観の家を訪れ、茶室に進もうとすると、なんと落とし穴に落ちて泥まみれになってしまいました。驚いた丿観は飛び出してきて、あやまりながらも用意してあった風呂に利休を入れ、泥を落とさせ、着物も取り替えたので、利休もすがすがしい気分で茶会に出席したということです。 この話には後日談があります。実は、利休は丿観が落とし穴を掘っていたことを知りながら落ちたというのです。どうして知っていたのに落ちたのですかと、ある人に聞かれ、せっかく掘った落とし穴に落ちないで、よけて通れば、亭主の趣向を無駄にすることになるので、わざとそうしたのだよ、と利休は答えたそうです。 なんとも言えない主客の茶の湯の楽しみ方ではありませんか。 ※「丿観」の漢字表記には「丿貫」とするものもありますが、今回は「丿観」を採用しました。 |