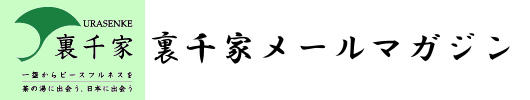 |
| 第44号(平成27年3月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『守破離』 伊住公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:第46回関東地区大会にて) |
|
こんにちは! 先日、今年のトップを飾る関東地区大会が行われ、久しぶりに鎌倉へ行ってまいりました。 鎌倉は鎌倉大仏、鶴岡八幡宮などの献茶式があり、多い時で年2〜3回は伺う機会があります。 しかしながら、ここ最近は鎌倉行事の時に私だけ他の用事が入り、すっかりご無沙汰続きでした。鎌倉は落ち着いた街並みの周辺にビーチが多いこともあり、どこか異国の香りが漂う感じがして私は好きな場所です。 昔の趣も大事にしつつ、現代にも即した街づくり。 “守破離”これは茶道だけでなく、文化全般にあてはまります。 私の亡くなりました父はこの言葉が大好きでした。 これからも日本文化が基本を守りながら時代に添って形を変え、未来へ続いていきます事を願っております。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:東陽坊長盛 ------------------------------------------------- |
| 京都の真如堂(しんにょどう)の僧侶、東陽坊長盛(とうようぼうちょうせい)は、「北野大茶の湯」に茶室を作って参加したとされ、長次郎作の黒楽茶碗「東陽坊」をはじめ、茶室、釜などにその名がのこっている茶人です。茶の湯は千利休に学びました。 ある時、豊臣秀次の家臣を茶会に招きましたが、忙しい人たちが多く、茶をゆっくり味わう時間がなさそうな雰囲気なので、東陽坊は機転をきかせ薄茶をわざと大服(おおぶく 茶の一服の量が多いこと)に点て、皆で飲み回すようにすすめました。濃茶は飲み回しが約束ですが、薄茶にはそのようなことはありません。それを東陽坊が始めたのです。その場の空気を察したとっさの判断だったのでしょう。 この話を聞いた利休は、東陽坊の作意を褒めたたえた、といいます。以後、薄茶を大服に点てて飲み回すことを「東陽にする」というようになり、東陽坊は「薄茶の先達(せんだつ=先駆け)」と、呼ばれたそうです。 |