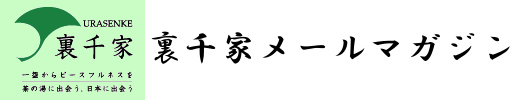 |
| 第43号(平成27年2月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『役割』 伊住公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:平成27年今日庵初釜式にて) |
|
こんにちは! 怒涛の一月が無事に終わり、「腑抜け」のような毎日です。 腑抜けというと言い方が悪いですが、それ程一月の初釜式は集中していたということです。 初釜式では式場を担当しております。 一日平均八席程の茶席で京都は一週間、東京は四日間行います。 お菓子を運び終わると敬史、私や弟、大谷、納屋はお家元が席中で濃茶を練られている間、水屋で息を殺しベストなタイミングを見計らって茶巾台、お茶を運び、お茶碗を下げる… 流れ作業にならず、一座建立、お客様に満足してお帰りいただける様に努めています。 水屋内でも様々な役割分担があり、下足番、迎え付けなど、一席の為に大勢の人間が携わり、連携する。茶道はチームプレーだなぁと改めて思った次第です。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:針屋宗春 ------------------------------------------------- |
| 京都市上京区に「針屋町」(はりやちょう)という町があります。場所は、裏千家の400mほど南、今出川通りから下がってすぐの小川通を挟んだ両側になります。ここは京都の豪商針屋一族の屋敷があったところで、町名もそれに由来するようです。 この針屋の一族に宗春(そうしゅん)という茶人がいました。宗春は、炉に釜をかけて火を絶やさないでおく「常釜」(つねがま)を心がけていましたが、これは、茶人の茶人たる基本的条件の一つでした。 ある雪の夜、京都の「聚楽第」(じゅらくだい、じゅらくてい)にいた豊臣秀吉が利休を呼び出し、「このような日でも京の町で茶の湯の準備に怠りない者はいるか」、と尋ねました。利休が「針屋宗春でしたら」、と答えたので、秀吉は利休に案内させて宗春のもとを訪れました。秀吉の突然の来訪に驚いた宗春でしたが、さっそく茶室に招き入れ、神様へのお供えを載せる「三方」(さんぽう)に洗米を盛って出し、茶の湯をしたので、秀吉は「我を神とするか」と、大いに喜び、宗春に褒美を与えたそうです。 |
| ------------------------------------------------------- 資料館学芸員出張所 ------------------------------------------------------- |
| 新春展「茶箱を楽しむ」 (併設展「季節の取り合わせ」) 1月7日(火)〜4月5日(日) |
| 茶を点てるのに必要な茶道具一式を小さな箱や籠にコンパクトに収納し、持ち運べるようにしたのが茶箱です。茶箱一つあれば、花見や紅葉狩り、旅行等の時に、手軽に抹茶を楽しむことができます。宝石箱を開けるようなワクワク感とともに、小さな茶箱の世界を覗いてみてください。 |
 |
| 菱文茶籠 無限斎好 3期展示(3/3〜4/5) |
| 裏千家14代無限斎が創案した茶箱点前・色紙点(しきしだて)のために好まれた茶籠一式。龍頭茶器、綾文蒔絵を施した象牙茶杓、黒釉と染付の茶碗2点、古帛紗等が仕組まれている。黒釉茶碗には、14代に因んで14本の金銀線が廻らされている。 |