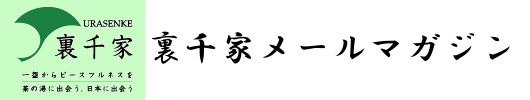 |
| 第41号(平成26年12月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『準備』 伊住公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:嚴島神社献茶式濃茶席にて) |
|
こんにちは! 13日は事始めでした。家元に直門、出入り方などが挨拶に来られ、あぁもうそんな時期かと一人感傷に浸っておりました。 私も30歳が近くなり、20代前半と比べると、一年が本当にあっという間に過ぎていきます。 事始めというのは、一年の感謝をお世話になった方にするとともに、越年準備を始めるという意味もあります。 今は、年末に慌てて買い物や準備をする方も多いですが、本来は時間をかけて準備するものなのですね。 宗家でも19日に稽古納めが終わりますと、新年、初釜式に向けての準備が本格化いたします。 今年も一年、メルマガにお付き合いいただき、ありがとうございました。 お陰様で出張に行く先々で、読者の方にお会いでき感想をいただけるのが何よりの励みです。 来年も良い年になりますように、皆様のご健康、ご多幸を祈念しております。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:北向道陳 ------------------------------------------------- |
| 千 利休の最初の茶の湯の師といわれる北向道陳(きたむきどうちん)は、堺に住み、北向の家に住んだところからそれが通称となったといわれます。本姓は荒木といいました。茶の湯は第39号(10月15日配信)で取りあげました空海に学んだといいます。 道陳は、ふくべ(瓢箪)の炭斗(すみとり)ただ一つを愛用し、炭の置き様は「道陳の炭さわり」と呼ばれるほど見事だったそうです。紹鴎を招いた時、茶室が西向きに建っていましたので「西日が入って具合が悪くはありませんか」と聞かれましたが、道陳が「茶会は朝しかやりませんから何も問題はありません」と答えたので、これにはさすがの紹鴎も二の句が継げませんでした。松屋久重が編纂した『茶道四祖伝書』にある話です。 道陳は、「すす(煤)はかず、門松立てず、餅つかず、かかる家にも春や来ぬらん」という和歌をいつも口ずさんでいたと伝えられます。この歌のどこにひかれたのでしょうか。 |