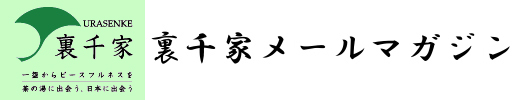 |
| 第38号(平成26年9月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『茶室披き』 伊住公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:立命館中学校・高等学校茶室披きにて) |
|
こんにちは! 仲秋になり、朝晩が随分と爽やかになってきました。 さて先日、立命館中学校・高等学校の茶室披きに行ってきました。 私は大学だけお世話になったのですが、そのご縁で伺いました。 立派な茶室、小学校から高校までの学生達の本当に生き生きとした点前に、お運び。校長自らお着物で道具のご説明。まさに学校をあげての素晴らしい茶室披きでした。 ただ最近の私学には驚きを隠せません。文庫から雑誌まで幅広いジャンルの書籍を揃えるメディアルーム、人工芝の陸上トラック付運動場、巨大な講堂、野球場まで!! 最近の学生達の恵まれた環境に驚き、この施設を活用できる彼らにジェラシーを感じつつ、お茶一服で心を落ち着かせたのでした。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:竹蔵屋紹滴 ------------------------------------------------- |
| 『山上宗二記』で「天下無双の花の名人」と評された堺の竹蔵屋紹滴(たけくらやじょうてき)は、名人にふさわしく「貨狄(かてき)」と名付けられた名物の釣舟花入を所蔵していました。「貨狄」とは、中国の神話伝説上の帝王黄帝(こうてい)の時代に舟をはじめて作った人の名前とされています。この花入は、後に織田信長の手に入りますが「本能寺の変」で焼失してしまいました。ロンドンの大英博物館に所蔵される『猿の草紙絵巻』の一場面には、花が入った状態の釣舟花入が描かれ、その横に「貨狄」と記されていますが、実物はこのような姿をしていたのでしょうか。 釣舟花入には、「出船」、「入船」、「泊舟(とまりぶね)」などの飾り方がありますが、これらは全て紹滴が工夫したものだとも伝えられ、茶花を投げ入れては、天地自然の理(ことわり)を観念して、ついには禅味を得たといわれた紹滴でした。 |