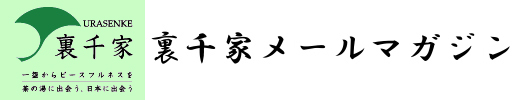 |
| 第37号(平成26年8月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『お盆』 伊住公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
|
こんにちは! 先週は台風が二つも発生し、大変な被害をもたらしました。 今後も発生する可能性が高いので、十分に気を付けたいものです。 さて、学生の方は夏休み期間中、社会人もお盆休みをとって帰省されている方が多いのではないでしょうか。 宗家でも、この時期になると東京の親戚が帰省し、皆でご先祖はじめ物故者の霊位に対してお供え物をし、読経いたします。 朝と夕方、二回のお勤めを13日から毎日行い、明日の送り火でご先祖達を見送るのです。 小さい頃は久しぶりに会う親戚と遊ぶのが楽しかった記憶があります。 盆というのは普段は離れ離れになっている一族が集う、そんな大切な日本の風習で、これからも大事にしていきたいですね。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:松屋久政 ------------------------------------------------- |
| 奈良の松屋久政(まつやひさまさ)は通称を源三郎といい、漆塗りを家業としました。現存する最古の茶会記『松屋会記』は、久政の一代前の久行の天文2(1533)年より始められ、以下、久政、久好、久重と都合、四代にわたり書き継がれました。 松屋は、5月号でご紹介しました古市播磨から珠光の茶の湯を直伝されたといい、所蔵する珠光名物「松本肩衝(かたつき)」、「徐煕(じょき)の鷺の絵」、「存星長盆(ぞんせいながぼん)」は「松屋三名物」といわれました。なかでも「徐煕の鷺の絵」にはわび茶の眼目(がんもく)とされる口伝(くでん)があり、それを会得すれば、天下無双の茶になるといわれましたが、不思議なことに所蔵者の久政はその口伝を知らなかったようです。 天正7(1579)年9月、久政は自宅に利休を招いた茶会で、珠光が表具の一文字を抜いて改装したことや、なぜ讃が無いのかなど利休から詳しく伝授されました。久政の二代後の久重が編纂した『茶道四祖伝書』(ちゃどうしそでんしょ)にある話です。 この絵は、中国・五代時代の画家徐煕により、絹地に白鷺二羽と蓮の花が描かれ、室町幕府の同朋(どうぼう)能阿弥が外題(げだい)を書いたものでした。 |