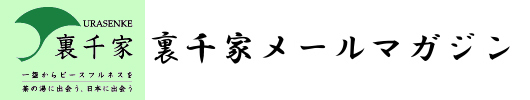 |
| 第36号(平成26年7月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『ご縁』 伊住公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:貴船神社献茶式にて) |
|
こんにちは! 毎日ジメジメと蒸し暑いですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 さて先日、関東の知人の方が稽古場を作られて25周年という事で記念茶会に参加してきました。 というのも私の父、伊住政和が稽古場の茶室建築に携わり、最初の席披きにも伺った『ご縁』があったからです。 茶道の世界に身を置き、月日を重ねる中で、「お父さんにはお世話になった」とか、「あの時のあの瞬間が忘れられない」だとか、息子の私にそれは熱心に思い出話をしてくれる方が沢山いらっしゃる事に気づきました。 それぞれの方と父との『ご縁』というものはとても大切で、息子の私にとって大事な財産です。 そういった事を考えると、梅雨の時期にもかかわらず、なんだか爽やかな気分になります。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:粟田口善法 ------------------------------------------------- |
| 『山上宗二記』で、宗二は茶人を四つのタイプに分けています。名物かざりをする「大名茶の湯」。道具の目利き(鑑識眼に優れた人)で、茶の湯も上手にでき、数寄の師匠として渡世(とせい)する「茶の湯者」。名物道具は一つも持っていないが、胸の覚悟、作分(茶の湯における独創的な工夫)、手柄(茶の湯における功績)、この三つを兼ね備えた「わび数寄」。そして「わび数寄」に加えて名物も持ち、茶の湯上手で志深い「名人」。 この四つのうちの「わび数寄」の一人で、京都の粟田口に住んだことから「粟田口善法」(あわたぐちぜんぽう)と呼ばれた人物は、「かんなべ(燗鍋=片口と弦のついた鍋) 一つにて食(めし)をも茶の湯をもするなり。身上(しんしょう)楽しむ胸のきれいなる者とて、珠光褒美(ほうび)候」と、宗二は書き残しています。たった一つのかんなべでご飯も炊けば、湯を沸かして茶も点て、名物といわれる道具も持たずに一生を送った善法。無一物の境地が茶の湯が目指すものだと考えていた宗二にとって、どうやら善法は理想の茶人の一人だったようです。 |