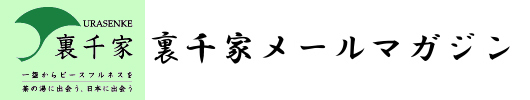 |
| 第34号(平成26年5月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『あっちこっち』 伊住公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:大宮氷川神社献茶式にて) |
|
こんにちは! 初夏を思わせる気温の高い日が続いていますね。 さてGWも過ぎ、宗家周辺も慌しくなってまいりました。 この頃から各地で献茶式、支部行事等が多くなり、大宗匠、家元をはじめ皆がそれぞれに出張なんて事もよくあります。 すでにこの5月に私も大宮氷川神社(埼玉)、竹生島神社(滋賀)の二ヵ所で献茶をご奉仕させていただきました。 明日からは青年部ナショナルコンファレンス2014、来週末には佐渡で第44回信越・北陸地区大会と行事が目白押しです。 そして今月末から、淡交会フィンランド協会25周年行事のため、単独でフィンランドに出張してまいります。 初めての単独での海外出張でワクワク、ドキドキ。張り切って行ってきます! また次回のメルマガでご報告しますね。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:古市播磨 ------------------------------------------------- |
| 珠光の弟子といわれた人々の中には、奈良郊外古市郷の土豪、古市播磨澄胤(ふるいちはりまちょういん)のような変わり種もいました。播磨は14歳で古市氏の菩提寺である興福寺発志院(ほっしいん)に入り、僧となる修行に入りますが、兄胤栄(いんえい)の隠退により還俗(げんぞく)して古市氏の家督を継ぎ、興福寺の僧兵隊長となります。 もともと古市氏は「淋汗(りんかん)の茶の湯」という入浴と酒宴を伴った遊興的な茶の湯を行っていました。播磨の場合も例外ではなかったのですが、何故か珠光に引き寄せられていったようです。そして珠光が播磨に与えたのが「心の文」と後に呼ばれた手紙でした。 この中で珠光は慢心をいましめ、達人に教えを請い、心の師とはなっても、心を師としないように播磨を諭したのです。珠光は、僧兵隊長から戦国大名へと成長していく播磨に不安なものを覚えていたようです。しかし『山上宗二記』では、「数寄名人。珠光の一の弟子」と高い評価が与えられているので、よほど茶の湯の修道に励んだものと思われます。 |
| ------------------------------------------------------- 今日庵文庫:新刊のお知らせ ------------------------------------------------------- |
| このほど、今日庵文庫は『茶道文化研究第六輯 特集 山上宗二記』を発刊いたしました。[B5版・定価2,160円(消費税込)] 『山上宗二記』は、天正年間の茶の湯を記した秘伝書として、すでによく知られています。本輯では『山上宗二記』に関する研究の現在、思想、茶室などの論文を収録し、また今回はじめて、今日庵文庫が所蔵する『山上宗二記』の全文を掲載しています。 内容はこちらからご覧いただけます。 [お問い合わせ・お申し込みは今日庵文庫まで Tel075-431-3434] |