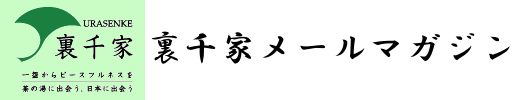 |
| 第32号(平成26年3月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『復興に向けて』 伊住公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:淡交会第122回総会にて) |
|
こんにちは! 3月も半ばに差し掛かりましたが、毎日寒い日が続きますね。 京都でも突然雪が降るなど、なかなか気温が上がってくれません。 昨年の今頃は20度以上を記録していたと思うと、ぞっとします。 さて、11日で震災から3年が経ちました。 いまだに避難生活を送られている方が約26万人もいらっしゃいます。 復興に向けて様々な問題もありますが、支援は継続していかなければなりません。 我々はこれからも微力ながら、お茶の縁を通じて、被災された同門の方々への支援を続けましょう。助け合いましょう。 よろしくお願いいたします。 |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話:珠光 ------------------------------------------------- |
| これまでは七哲を始めとした利休周辺の茶人の逸話を取り上げてきましたが、今回から利休以前の茶人をとりあげてみましょう。 珠光(しゅこう)は、「わび茶の祖」とされる人物ですが、生存中の確かな史料が少なく、謎の多い人物です。しかし後に利休の弟子山上宗二によって書き記された『山上宗二記』(やまのうえそうじき)には、珠光のさまざまな伝承が集められています。 同書によれば、珠光は一休和尚に参禅し、悟りを開いた証として、墨蹟(ぼくせき)の第一とされる中国・宋代の高名な禅僧・円悟(えんご)の墨蹟を譲られ、それを掛けて日々茶の湯を楽しんだそうです。そして「投げ頭巾(なげずきん)」という唐物茶入を手に入れた後はこれを愛蔵し、跡目(後継者)の宗珠に「私が亡くなったら命日には円悟の墨蹟を掛け、『投げ頭巾茶入』に挽屑(ひくず)を入れ、茶碗へその抹茶をすくい入れ湯を注いで供養せよ」と言い残したということです。 挽屑とは茶の挽き屑のことで、下級な抹茶をさします。珠光は挽屑を「投げ頭巾茶入」に入れさせることにより、この茶入を唐物でありながら「わび道具」として扱うべきものであることを、掛物に墨蹟を用いることで珠光のわび茶が禅宗を拠り所とすることを、それぞれ示そうとしたのでしょう。 また同書には「わらやに名馬を繋ぎたるが好し」と、珠光が粗末な座敷で名物の道具一種を茶に用いるのが面白いと言ったとありますが、これは「投げ頭巾茶入」と挽屑の関係に通じるものといえましょう。 |
| ------------------------------------------------------- 茶道資料館:学芸員出張所 ------------------------------------------------------- |
| 春季特別展「光悦・等伯ゆかりの寺 本法寺の名宝」 (展覧会開催期間)3月14日〜5月18日 |
 |
| 重要文化財 花唐草文螺鈿経箱 本阿弥光悦作 展示期間 4/22‐5/6 |
| この光悦作の花唐草文螺鈿経箱は、螺鈿によって花唐草文様が描きだされた優美な経箱です。見る角度で変わる螺鈿の輝きを写真ではお伝えできないのが残念です。 箱の蓋に段差があることにお気づきになることでしょう。平成14年に修復がなされた際、すでに蓋の側面部分が失われていたため、新たに黒漆塗の蓋が作られました。現在は新しい蓋の上に、元の蓋が載った形になっており、そのため段差が生じたのです。当初はこの蓋側面の部分にも文様があったと考えられます。なお修復は重要無形文化財保持者の北村昭斎氏により行われました。 展覧会図録の表紙は本作品の花唐草文様を生かしたデザインを採用し、螺鈿の輝きを実感できるように仕上げました。ぜひ会場でお手にとってご覧ください。 |